DUMB TYPEパフォーマンス作品連続上映会(トークイベント抄録をアップしました!)
レポート
DUMB TYPEパフォーマンス作品連続上映会「トークイベント」抄録
東京都現代美術館にて開催された「ダムタイプ|アクション+リフレクション」と連動し、2019年11月25日から12月1日まで御茶ノ水Rittor Baseで行った「ダムタイプ パフォーマンス作品連続上映会」。各日の最終回には作品のクリエイションにかかわったメンバーをお招きしてトークイベントを開催しました。その抄録を掲載します。
-
INTERVIEW國崎晋(Rittor Baseディレクター)
Day 1 -「036-Pleasure Life」 after talk with 山中透 (2019年11月25日)
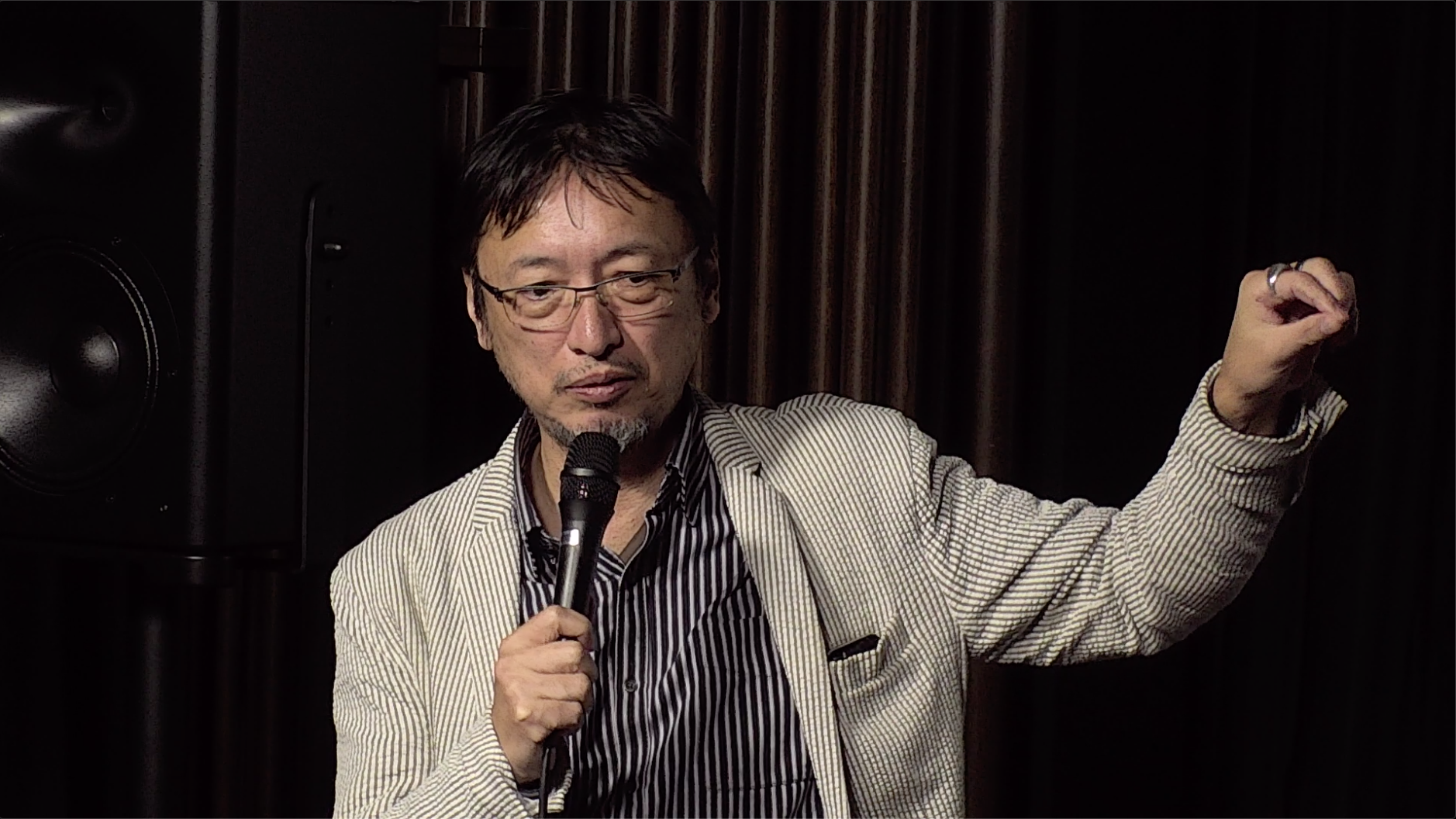
●古橋悌二との出会いとダムタイプへの参加
──「036-Pleasure Life」の話に入る前にお伺いしたいのですが、山中さんは“ダムタイプの創設メンバー”という言い方をしていいのでしょうか?
山中 そうですね。ダムタイプは元々は京都芸大(京都市立芸術大学)の学生を中心に結成された、“座・カルマ”という劇団サークルから発生したグループなんですが、僕は学外……関西大学だったんです。でも、(古橋)悌二とは大学に入る前からバンド仲間だったので、悌二が京都芸大に入ったらそのまま活動を手伝うというか、座・カルマの時はビデオ撮影をしたりとか、自然発生的に巻き込まれていった感じですね。
──悌二さんとは高校時代からの知り合いだった?
山中 いや、高校を卒業したくらい……僕が大学入った19歳ぐらいの時ですね。悌二は高校卒業後、2年間は大学に行かずにバンド活動をしてたんです。
──2人でどんなバンドをやっていたのですか?
山中 ニューウエーブっていうか、当時はやっていた音楽を基盤としたようなバンドでしたね。3人組だったんですけど楽器の編成がちょっとおかしくて、僕がボーカル、悌二がマリンバとパーカッションとリズムマシン、そしてもう1人がキーボード(笑)。
──そのバンドで一緒に活動する流れで、座・カルマそしてダムタイプのお手伝いをするようになったと?
山中 そうですね、元々僕も別のサークルでパフォーマンスというか、ジョン・ケージとかに始まるような現代音楽をやっていて、どんどんパフォーマンスに傾いていったんです。当時、演劇のフィールドだと一番趣味だったのは寺山修司さんの天井桟敷。僕らのちょっと上の世代の人がやってたんで、ある意味憧れって言うか……天井桟敷もミュージシャンから美術家までいろいろなアーティストがそろってますよね? そういう総合的な舞台がカッコいいなと思うようになってたときに、悌二が京都芸大に入って、そこの若いアーティストの中で才能のある人をつかまえて作品作りを始めた。そうこうしている内に悌二がバンドをやめて演劇の方に集中したいと言ったので、僕も引っ張られるような感じで、気付いたらダムタイプにいたという感じです。
──今回の連続上映会の中で、今、見ていただいた「036-Pleasure Life」が最も古い作品でしたが、それ以前の記録映像は無いのですか?
山中 記録が無いってことはないですが、“ダムタイプ”って名乗ったのが、この「036 Pleasure Life」からなんです。その前は“ダムタイプシアター”という名前で、実質、まだ京都芸大のサークルでした。1985年の「風景収集狂者のための博物図鑑」っていう作品の音楽を悌二と一緒に作ったのが、多分、ダムタイプシアターって言われる頃の僕のとっかかりだと思います。それから学外……アートスペース無門館っていうスペースで「庭園の黄昏」、近鉄小劇場で「睡眠の計画 #5」でも、悌二と一緒に音楽を作りました。
──「036-Pleasure Life」からは学生サークルではない形態になったということでしょうか?
山中 そうなんですけど、そうでもないところもあるんです。悌二と僕は卒業していたんですけど、他のほとんどのメンバーはまだ学生だったので。ただ、「036-Pleasure Life」は学校から離れた団体になろうという、決意の作品だったんだと思います。
●パフォーマーの音に反応する音響システム
──記録映像を拝見すると、この「036-Pleasure Life」は観客が舞台を上から見下ろす構造のように見えますが、そういう作りだったのでしょうか?
山中 はいそうです。公演で使ったアートスペース無門館は自由に客席を作ることができるフリースペースなので、客席を組み上げてそこから観ていただく形です。「pH」もそうですけど、ダムタイプは昔から上から映像を投影するのが好き(笑)。それに加えて「036-Pleasure Life」では正面に4つのモニターを置いています。SONYの26インチのブラウン管……Profeelですね。あの当時、市販されているモニターでは最大だったと思います。
──今回の東京都現代美術館の個展「ダムタイプ|アクション+リフレクション」でも、過去のパフォーマンス作品のダイジェスト上映にProfeelが使われていましたね。
山中 “ビデオアートといえばProfeel”っていう感じでしたからね。ナム・ジュン・パイクさんも使っていたし。当時、三管のプロジェクターもあったとは思うんですけど色味が薄かった。画像をはっきり映せるのはブラウン管だけだったんです。
──「036-Pleasure Life」の舞台装置ですが、床に人工芝が敷かれ、その真ん中に6×6=36のマスが組まれているという理解でいいですか?
山中 はい。マスの部分にはタイル状のものを置いて、四辺を取り囲むように蛍光灯を配置し、そこにマイクを設置しています。パフォーマーが立てる音をそのマイクが拾って、それをトリガーとしてサンプラーが音を鳴らすようにしていたんです。当時、AKAI PFOFESSIONALのS900っていうサンプラーを借金して買ったばかりで、嬉しいからもう使いたくて仕方ない(笑)。トリガー信号を受けるASK-90っていうオプション・ボードをS900に取り付け、パフォーマーが“ドン”と足踏みしたら、その音をマイクが拾って“I love you”とか“I hate you”とかいう音がサンプラーから鳴る。結構誤動作が多かったんですが、まあそれもありかと。
──サンプラーを舞台で使っている方はまだそんなに多くない時代ですよね?
山中 多分、ローリー・アンダーソンくらいじゃないですかね。僕らもローリーがやったのを見てやりたいって思いました。
──「036-Pleasure Life」では、サンプラー以外にどんな機材で音を鳴らしていたのですか?
山中 あのころ音楽の再生にはオープンリールのテープデッキを2台使っていました。
──ダムタイプの舞台というと、映像と音がバキバキに同期するイメージが強いですが、「036-Pleasure Life」の時代も同期システムは使っていましたか?
山中 いや、同期できたらいいなとは思っていましたが、まだそういうシステムを入れてませんでした。さっき言った4台のブラウン管に「S/N」でも使ったオシロスコープの波形が映し出されるんですけど、それに合わせて“ピコーン”という音を鳴らそうと思ったんですが、映像の送出に使っていたのがVHSテープで、そこに音を入れるとすごく音質が悪い。どんだけやってもクリアな音が出なくて、オープンリールから再生している僕の曲との落差が激しいんです。かと言って同期もできない……なので、その“ピコーン”という音は手で弾いてました(笑)。
──ライブで、ですか!?
山中 はい。オペレーション・ブース内にアシスタントの人がいまして、彼女がブラウン管を見ながら“山中さん、Aの音、今です!”って言うのに合わせて僕が“ピン!”っていう音を弾いて、次に“Bの音です”って言われたら“ポン”って音を弾くとか、そんな感じ。人力の方が意外とシンクロするっていうか、そっちの方がかっこええし(笑)。バレへんかったらええやろうという感じでやってました。オペレーション・ブースにはさっき言ったオープリールのデッキとサンプラーのほかに、YAMAHAのDX7というキーボードが置いてあって、“ピン”という音はそのDX7のプリセットのエレピ音を使ったと思います。悌二も僕もあの音が大好きで、当時はそればかり使ってましたね。実はあの音が4人のパフォーマーへのキーになっている……それぞれにAとかBとか固有の音高が与えられていて、自分の音が鳴ったらパフォーマーはそれに反応して動くんです。
──今のお話を伺っていて思い出したんですが、私が1995年にスパイラル・ホールで「S/N」の取材をした際、ホールの調整室に行ったらAKAI PROFESSIONALのMPC60IIが置いてあって、ヒップホップの人たちが使うことで有名なサンプラー/シーケンサーを何に使っているんだろうって疑問に思って尋ねたら“パフォーマーの動きに合わせてたたいている”って(笑)……そういう意味では「S/N」の頃まで割と人力で音を合わせていたのですね?
山中 手の方が早いですから(笑)。そもそもパフォーマーがステイブルじゃない……「S/N」でパフォーマーがホリゾントの方に仰向けで倒れていくシーンがありますが、毎回倒れるタイミングも倒れ方もスピードも変わったりするので、そこに合わせて“ドーン”という音を鳴らそうと思っても同期システムだったら絶対合わない(笑)。最初は冗談のつもりでパフォーマーが倒れるときに“ドーン”という音を入れてたら、悌二とかみんなが“それいいね!”っていうことになって、やらなければならなくなったんです(笑)。
──では、毎回パフォーマーの動きを目で追いながら?
山中 たまにステージを見てなくてたたいてない時がありますけど……あ、忘れたって(笑)。でも、お客さんは“今、鳴らなかってことには何か意味があるに違いない”って思ったり。それがミソなんですよ(笑)。どうぞ考えてくださいっていう。
●古橋悌二とのコラボレーションによる曲作り
──ダムタイプでの曲作りについて伺いたいのですが、当初は山中さんと悌二さんとで合作していたという理解でよろしいですか?
山中 はい。僕がまずスケッチ……それこそベーシックなコード進行くらいのものを悌二に渡して、それを悌二がいろいろこねくり回してまた僕に返す、という感じで、2人で寄ってたかってアレンジしながら作っていきました。「036-Pleasure Life」のときは、悌二が1年前にニューヨークに留学してたんで、その間、僕はずっと大阪でせっせとデモテープを作ってたんです。サックスの音が聴こえたと思いますが、あれはkitteさんという大阪の学生さんが吹いたもの。実は「036-Pleasure Life」のテーマになっているジャズっぽい曲は公演直前までできてなかったんです。僕が「睡眠の計画」の時に作った曲を使うということになっていて、パフォーマーもみんなそれでやるつもりで練習してきたんですけども、本番の3日前ぐらいになって悌二に“ええ曲できたで~”ってあの曲を聴かせたら、急遽それに差し替えることになった(笑)。
──悌二さんとやり取りしつつアレンジを進めたということですが、今だったらパソコンを使ってファイルのやり取りで簡単にできますけど、当時はどんな方法だったのでしょうか?
山中 カセットテープでしたね。あとは僕のスタジオに悌二が来て、2人で朝から晩までセッションして、夜になったら一緒にゲイディスコに行って、朝方に帰って来てまた続きをやる……非常に体に悪い毎日でした(笑)。
──2人でセッションする場合はどんな楽器を弾いていたのですか?
山中 2人ともキーボードです。スタジオには2台のシンセサイザーがあって、悌二はほとんどYAMAHA DX7で、僕はCHROMA Polaris。僕はたまにギターを弾くこともありました。
──悌二さんがドラムを叩いたりは?
山中 ドラムはたたきませんでしたけど、リズムマシンの打ち込みがうまくて、それこそドラムソロがたたけるくらい上手。なので細かいニュアンスのリズムは全部悌二に打ってもらってました。
──2人で作業された山中さんのスタジオはどんなところだったのでしょうか?
山中 普通のマンションの6畳くらいの部屋。悌二と一緒に天井まで布を張ったりして、いろいろなレイアウトをして遊びながら作った場所です。ミキサーをぽんと置いて、その周りにキーボードを2台置いて、それで音を出せるようにしていました。後にターンテーブルを導入して、効果音とかレコードの音をたくさん使ってミックスするようになりました。
──そういったDJカルチャー的なものは、悌二さんがニューヨークで吸収してこられたのですか?
山中 いや、悌二がニューヨークに行く前からですね。1984年くらいに京都にマハラジャっていうクラブというかディスコがあったんですけど、そこのお手伝いを少ししてたんですよ。2人とも元々ディスコが好きでしたが、そのころちょうどハウスミュージックが盛り上がってきて、これまでのディスコとは何か違う新しいダンスミュージックだなと。その後で悌二がまさしく現場で体験してきて、それを持って帰ってきたという感じですね。
●音楽が先か振付が先か
──悌二さんと山中さん以外のダムタイプのメンバーは、音楽に対する関心はどれぐらいあったのですか?
山中 まあ、音楽は好きだったと思いますよ。ただ、よう触らへんというか、悌二の作ったものに対して誰も文句を言わなかった気がします。
──悌二さん時代のダムタイプでは、そもそも音楽が先にできて、振付というかパフォーマンスはそれに合わせて作っていたのでしょうか?
山中 場合によりますね。始めから曲ありきだったのが多かったと思いますけど、僕は曲を作るのが遅いので、曲ができるまでに悌二が勝手に振付を作っていたこともあります。スケッチというかガイド的なものは先に渡してるんですけども、“この曲ではあかんやろう”ということになって、もうちょっといい曲を僕が頑張って作るっていう感じでした。
──山中さんがバンド活動からダムタイプに専念するようになったのは、パフォーマンス作品のクリエイションが面白かったということですか?
山中 面白かったですね。カッコイイ舞台装置の中に生身の人間が出てきて、そこに照明が当たってっていうのが、やっぱりね。パフォーマーの動きやそのシーンに対して効果的な音はどんなものがあるだろうと探すことがとても刺激的でした。
──舞台装置もいいし照明もいい……先程悌二さんが京都芸大で若いアーティストを集めたという話がありましたけど、1つの大学にそれほど才能豊かな人達が集まっていたというのは不思議ですよね。
山中 ですよね(笑)。
──集団でのクリエイションを才能豊か、そして個性の強い方々でできていたのも不思議です。きっとさまざまなあつれきもあったと思うのですが。
山中 仲はむちゃくちゃ悪かったですよ(笑)。僕と悌二は基本的にはケンカというか言い合いばかりしてた。やっぱり気にくわないところは気にくわない……“そのアレンジあかんやろ!”とか。それでも時間が来たら“じゃあ、ゲイディスコ行こうかー”って感じ(笑)。
──そこでリセットされる(笑)。
山中 リセットというか、またゲイディスコへ行かなあかんの怖いなーって(笑)。
──怖かったんですか?
山中 怖い怖い……目線が怖い(笑)。悌二はもちろん大好きでしたけど。さっきも言いましたけど、ゲイディスコから朝に帰ってきて、ちょっとだけ寝て、そのあと昨日の懸案をどうするかを時間がある限りお互いやり合ったりするんです。
──それは喧嘩と言うより、すごくクリエイティブな作業ですね。
山中 悌二は京都出身で僕が大阪。大阪の人はむちゃくちゃ切れるけど、向こうはもうのれんに腕押し。怒ったら損するなぁ~と思って我慢するんですけど、我慢できへんようになってまた爆発して、悌二はまたのれんに腕押しでしたね(笑)。
Day 2 -「Pleasure Life」 after talk with 山中透 (2019年11月26日)

●「036-Pleasure Life」と「Pleasure Life」の関係性
──今回上映した「Pleasure Life」は「036-Pleasure Life」とタイトルが似通っています。2つの作品はどういう関係なのですか?
山中 「Pleasure Life」は「036-Pleasure Life」の続編と思っていただいていいです。そもそもは海外ツアー絡みなんですよ。1988年、ダムタイプが初めて東京で公演をし、その後に海外ツアーに出るって話になった。でも、「036-Pleasure Life」は観客が舞台を上から見下ろす構造で、そんな舞台を組めるような劇場はなかなか無い。なのでコンセプトを一緒にしながらも違う作品を作ろうということでできたのが「Pleasure Life」。あと「036-Pleasure Life」の直前、1987年に「サスペンスとロマンス」っていうインスタレーション&ライブを兵庫のつかしんホールでやったんですが、その要素も若干反映されています。
──続編ということで、確かに音楽も「036-Pleasure Life」と同じものが幾つか使われていましたね。
山中 「036-Pleasure Life」の曲をベースにしてるんですけども、リミックスしたり、新曲を2曲くらい足したりしています。“今、一番かっこいい音楽はなんやろ?”と考えていて、「036-Pleasure Life」の時はまだピンと来てなかったんですけども、「Pleasure Life」のときはハウスミュージックをやったろって決めてたんです。あとはアンビエント……“アンビエントが流れる美術作品の中で人が動く”っていう構想です。
──普通の劇場でやりやすくするために、どのような舞台構造にしたのでしょうか?
山中 「036-Pleasure Life」のグリッド構造だけはコンセプトとして残したいんで、メンバーでいろいろアイディアを出して、プラットフォームと呼んでいる細長いフレームで作られたものを6基×6基=36基置くことで、客席からも分かるような大きなグリッドを作りました。
──プラットフォームにはブラウン管などいろいろのものが載せられていましたね。
山中 はい、上に載せているだけでなく、フレームの中に蛍光灯とかいろいろなものを仕込んでいました。1989年にはそのプラットフォームを使ったインスタレーションを「プレイバック」というタイトルでサンフランシスコ近代美術館で展示したんです。今回の東京都現代美術館「ダムタイプ|アクション+リフレクション」で展示している「プレイバック」のもととなる作品ですね。今回の展示では今風な作品に変わっていますが、そこでプレイされている音は「Pleasure Life」で使われた僕と悌二の音だったりします。
──そもそもグリッドにはどのような意味があったのでしょうか?
山中 ルール……ゲーム的なルールを作った環境の中に人を置いてみようっていうものです。実際の舞台ではそのグリッドに対して作品をインスタレーションみたいにどんどん作っていく形で、「036-Pleasure Life」の場合は最後に何か1つの街みたいなものに変貌する。「Pleasure Life」の時には最初からある程度建物が建っていて、何か煙突からもくもく煙が出たり……そういう意味でも前作の続きなんです。
──主要キャストが4人のパフォーマーというのも2作品共通ですよね。
山中 悌二と(薮内)美佐子のアジア人男女と、カティア(サゼヴィッチ)とジェイムス(シンクレア)という白人男女。「Pleasure Life」では美佐子は中国語をしゃべって、カティアはロシア系アメリカ人なんでロシア語をしゃべって、それでジェイムスは英語をしゃべって、悌二は日本語をしゃべってたはずなんですけどあんまり喋ってない……あんまりしゃべらない日本人ということで(笑)。そういうキャラクター設定が「036-Pleasure Life」のときは曖昧で、なんぼでも突っ込みどころがあって、それをどんどん削っていって「Pleasure Life」になっていった。2つの作品を観たら氷解するようなところがあるかなと思うんです。
●古橋悌二の留学を経て実現した海外ツアー
──「Pleasure Life」を作るきっかけとなった海外ツアーですが、そもそもどういう経緯で実現したのでしょう?
山中 1986年に(古橋)悌二がニューヨークに留学して、その時の人脈で1988年の第1回ニューヨーク国際芸術祭っていう超巨大なイベント……第1回のままで終わってしまったんですけど(笑)、そのイベントに来てほしいというオファーをいただいたんです。
──悌二さんの人脈というのは舞台関係の方々?
山中 はい。悌二はメレディス・モンクのカンパニーで衣装の縫子さんみたいなアルバイトをしていて、そこに僕のデモテープを置いてきたと言ってました(笑)。後年、メレディスに会うことがあって、“あの時のデモテープって覚えてます?”って聞いたら“覚えてます”って言われました。メレディスはニューヨークを拠点にボイス・パフォーマンスをしたり、演出をしたり、舞台作品を作っている人で、今もなお新作を作っています。悌二は前からメレディスのレコードとかたくさん持っていて、ある種ファン的な心情だったと思うんです。それでニューヨーク留学中にメレディスのカンパニーによく遊びに行ってたらしい。
──昨日のトークでは憧れだったのが天井桟敷だったり、参考にしたのがローリー・アンダーソンだったという話がありましたけど、メレディス・モンクにも影響を受けていたのですね?
山中 そうですね。ただ、当時、実際の舞台は見たことがなかったです。レコードで……音で想像するしかない。ネットも無い時代で本も手に入らないから、ニューヨークで何が起きてるのかっていうのは実際に行ってみないと分からない。それで悌二は自ら行くことによって現場に触れ、そこからいろんなことが始まったような気がします。
──縫子のアルバイトをしてカセットテープを置いていくという話は驚きですが、舞台作品を売り込むために、悌二さんはほかにどういうことをされていたのでしょう?
山中 一軒一軒、ドアをノックするような感じじゃないですかね、多分。ニューヨーク国際芸術祭での「Pleasure Life」はP.S.122というスペースで上演したんですけど、そこのプロデューサーのマーク・ラッセルとは留学時代に知り合ったと悌二は言っていました。悌二が死んでしまったからその辺の詳しい交友関係も分からなくなっているんですけど、留学中に相当人脈を広げていったみたいで、1987年に帰国した時には、“ニューヨークでやる!”って鼻息荒く言ってました。
──リーダー格の古橋さんがぽーんとニューヨークに行ってしまい、1年後に帰ってきたら“次はニューヨーク!”となって、ほかのメンバーは面くらいませんでしたか?
山中 まあ、行けるんやったら行きたいっていう感じで。まだ学生がほとんど……大学を卒業していたのは多分、僕と悌二と小山田(徹)ぐらいじゃなかったかな。だから卒業旅行みたいだったんじゃないでしょうか。
●“ダムタイプ爆音時代”の始まり
──先ほどのお話によると、「Pleasure Life」の初演は東京だったのですか?
山中 そうです、原宿クエストホールです。
──まず東京で公演したというのは、この舞台セットで海外を回れるかどうかを確かめる意味合いもありましたか?
山中 そうですね。実はあのプラットフォームは全部パッキングできるようになっていて、メンバーの手荷物で運べたんです……舞台セットを手荷物で運ぶカンパニーなんてないですよね(笑)。カッコ悪い話なんですけど、プラットフォームのフレームを入れる細長い長方形の箱の中に、メンバーの替えの下着とかをクッション代わりに入れてました(笑)。
──ニューヨーク国際芸術祭から招待といっても、そんなにバジェットが出たわけではなかった?
山中 ほとんど持ち出し。海外公演ができたのはメンバーの多くが学生だったからです。僕とか悌二、小山田は卒業していたからむちゃくちゃ金がなくて、しかも3カ月の長期のツアーになるからバイトも首……。
──学生メンバーは別に3カ月間収入がなくてもいい?
山中 3カ月のツアーの中で一度日本に帰ったやつもいるし、パリとかローマに旅行に行ったやつもいる。悌二も彼氏がいたからパリに遊びに行って、僕は小山田と2人でロンドンのB&Bの安ホテルに泊まって……もうたまらず、知り合いのミュージシャンが居たウェールズに小山田1人を残して行った。いまだに“あれは最悪やった”って小山田に言われてます(笑)。
──潤沢な資金があったわけでもないのに海外ツアーに出たのは、自分たちの作品が海外で通用するかどうかを確かめたかったからですか?
山中 はい……というか僕らはもう自信満々でしたから(笑)。
──実際、現地での反応はどうだったんでしょう?
山中 ニューヨークは受けました。P.S.122というスペースは元々小学校か何かの跡地という結構大きな空間で、床が汚なかったり、設営の時間があまりなくて徹夜続きだったり、泥棒にも入られたりと大変だったんですけど、空間の雰囲気と作品とが合う感じで、お客さんの反応も良かった。何人かのミュージシャンが声を掛けてくれて、お互い住所を交換して連絡を取り合うようになりました。さっきのウェールズのミュージシャンもそのときに知りあったんです。
──出来栄えとしてかなり良かったのですね。
山中 でも、悌二の舞台上でのアクションは何か二歩くらい多かったんですよ……動けなくなってるんじゃなくて動き過ぎ。これはぜったいキメてるなと。あの時代のニューヨークは街中がドラッグとハウスミュージックだったんですが、とはいえ“大事なステージで、みんなが酒を飲むのも我慢してるのに、何で1人で羽目外してキメてるんだって!”って説教しましたよ。でも、後から分かったんですけど、そのころ悌二は自分がHIVポジティブだってことを知ったんですね。なのでそういう風になっても仕方がなかったのかなと。
──ニューヨークの後はどちらで公演を?
山中 ドイツです。ミュンスターというデュッセルドルフの近くの街。そこはもうスピーカーがボロボロで大変でした。館長にさんざん文句を言って、ようやく少し改善されてある程度の音量が出るようなって初演を迎えました。大変だったんですけど、ドイツではむちゃくちゃ受けましたね。足踏みがすごくて劇場が揺れて怖くなるくらいでした。
山中 ドイツの人たちはダムタイプをどういうものとしてとらえたのでしょう? 演劇でもないし、ダンスでもないし……。
山中 全体的な作品の内容を観て、その在り方がいい、ということをいろいろ言われた気がします。あと音楽の評判もすごく良かったですね。まあ、音楽はドイツよりロンドンの方が受けたかな。
──ドイツの後にロンドンだったのですか?
山中 はい。ちょっと変則的だったんですがロンドンに1カ月滞在して、初めの1週間で公演をやって、その後に休みがあって……さっきも言いましたようにその間にみんないろんなところに行って(笑)、その後ロンドンでもう1週間やるという形だったんです。
──不思議なスケジュールですね。
山中 ええ。で、最初の1週間の上演の時はお客さんが途中で帰ったりして、すごいイヤだった。それでいろいろと試行錯誤したんです。そのころの僕はデリケートな音を信条としていて、音の継ぎ目が分からないくらいきれいにつないだり、音も全部の帯域をちゃんと出したりしていたんですけど、あまりにもお客さんが帰ったのでやり方を変えたんです。「Pleasure Life」の終わりの方のシーンでブルドーザーのおもちゃが“ブインブインブイン~”ってバイクみたいな音を出してますけど、あそこで耳が痛いくらい……“お前ら死ねやー!”みたいな音を出してみたら、帰ろうとしていたお爺さんがもう1回座ったんです。“これがヨーロッパ人に対する方法かー!”と思って、そこからダムタイプの爆音時代が始まるんです(笑)。
──山中さんはダムタイプでは音楽担当ということでしたが、ツアーの時はPA……音響担当もしていたのですよね。
山中 はい、PA的なことは全部。それこそ海外の劇場の人たちはスピーカーをごんっと持ってきて、はいって置いていくだけで、あとは何もやってくれないですから。配線も自分でやっていました。
──アシスタントもなく1人で?
山中 1人ですね。悌二も演出の方で忙しくて、たまにちゃちゃ入れに来るだけでした。
──当時のダムタイプは音響、照明などのスタッフは1人ずつだったのですか?
山中 そうですね全部門がほぼ1人。ダムタイプはとにかくプロダクションがギリギリ過ぎて、「Pleasure Life」の初演……原宿クエストホールでの初日になっても、実はエンディングのシーンを決めてなかったんですよ。
──ええっ!
山中 本番の直前まで徹夜が続いていて、エンディングをどうするかっていう打ち合わせをするのを完璧に忘れていたんです(笑)。で、本番が始まってだんだんシーンが終わりの方に近づいてくるじゃないですか。そこで“ん?ちょっと待てよ”と(笑)。当時、僕らはやっとインカムを使い始めたから、みんなでインカム越しに“エンディング決めてませんよね”って相談を始めて(笑)。悌二も舞台出てるし。それで僕と小山田、照明の高谷(史郎)、スライドと映像の穂積(幸弘)という4人で“どうする?どうする?”という感じになって、“分かりました、僕が音をフェードアウトするので照明も一緒に下げて終わり”って(笑)。
──舞台上の悌二さんたちにそのプランを伝えられたんですか?
山中 “そうやるで~”ってことを小山田に伝えてもらいました。ほんまにひどいグループですよね(笑)。
●池田亮司との出会いと新たなコラボレーション
──その後、新作のたびに海外ツアーに出ることになりますが、それは「Pleasure Life」が各国で評価されたからですか?
山中 はい、幸いなことに毎回呼んでいただけるようになりました。プロデューサーは最初はアメリカの人でしたが、1980年代後半からアメリカがどんどん経済的に厳しくなっていったので、「pH」のツアーのときはヨーロッパのサポートが大きかった。その後「S/N」のツアーの途中からはフランスのプロモーターの人が頑張ってくれました。「S/N」はAIDSを取り上げていて、パフォーマーも黒人や耳の聞こえない人、HIVポジティブを出すっていう段階で、アメリカからはそっぽを向かれました。今でいうポリティカル・コレクトネスみたいな感じがあったんではないでしょうか。
──「S/N」はニューヨークでこそ公演したかった作品ですよね?
山中 はい、悌二は本当にニューヨークでやりたかったみたいなんですけども、結局アメリカで唯一公演ができたのはシアトルで、それも初日にパフォーマーが舞台から落ちて大けがをして残りの公演が全部キャンセルになった。
──「S/N」の公演は1994年にオーストラリアのアデレードから始まり、1996年までとかなり長く行われました。
山中 はい。悌二が亡くなってからも続けていました。でも、悌二が亡くなってから僕はツアーに参加しなくなりました。ほかの活動も始めていたのでスケジュールが合わなくなってきたんですよ。
──それで音響のオペレートを池田亮司さんが担当されるようになった?
山中 そうです。ツアーの途中で亮司君に“ちょっとついてきてよ~”って言って、どんどん任せるようにしたんです。
──池田さんは「S/N」のサウンドトラックというかCDをスパイラルのレーベルからリリースした際のプロデューサーでしたよね。私が最初にダムタイプの取材をしたのはまさにそのリリースのときで、山中さん、古橋さん、そして池田さんへのインタビューを行いました。あのときダムタイプでCDを出すというのは、どういう流れで決まったのですか?
山中 亮司君に口説かれたんです。僕と悌二からすると「S/N」の曲って言われても、自分たちで作ったのは2曲くらいしかなくて、あとは他人の曲ばかり……「ピープル」はシャーリー・バッシーだし、「アマポーラ」はナナ・ムスクーリ。ほかにもサイモン・フィッシャー・ターナーや亮司君が作った『silence』ってコンピレーションに入っている東野珠美さんの笙の曲も使っている。それらの権利関係をクリアするのが大変だって。
──それでも池田さんはCDを出したいと?
山中 ええ。それで昔のパフォーマンスで使った曲を加えるので良かったらってことで作ることにしました。
──「S/N」のCDはもう手に入らないですよね?
山中 実は2020年にアナログ盤を出そうという話があります……それは僕と悌二の夢でもあったんで。高谷もすごい乗り気ですね。やっぱりデザイナーなのでジャケットが大きい方が腕の奮い具合がある。未収録の音源も加える予定ですのでご期待ください。
──「S/N」のCDを制作する作業を通じて、池田さんが使える人材だと分かり、海外ツアーに誘ったのですか?
山中 “この人ちゃんとできるし、ええやん”と思って。
──その後、池田さんは音響オペレーターだけでなく、「OR」からは音楽家としてもダムタイプに参加するようになります。昨日のトークで山中さんと古橋さんがどうやってダムタイプの音楽を作っていたかを伺いましたが、池田さんとはどうやって作っていたのかを教えてください。
山中 亮司君との場合は、それぞれが曲を出し合う感じですね。彼の方が作るのが早くて、気がつくとほぼ終わってる。なので僕は隙間産業を狙い、ちょっと気の抜けた曲とかを作ります。「OR」だと怖い“ピッ”とか“プスッ”という音は大体亮司君。聴いたら絶対分かります(笑)。でも、亮司君が作った冒頭の曲に、僕が作りかけていた曲のストリングスを無理やり乗せたりはしていますね。
──“ピッ”っていう短いサイン波の音は池田さんのトレードマーク的な音として知られていますが、今回ダムタイプの作品を改めて観直すと、池田さんが入るよりもかなり前から使われていたことに気付きました。
山中 ちょっと柔らかい“ピッ“……痛くない“ピッ“ですけどね(笑)。あれは僕と悌二の趣味です。亮司君はその“ピッ“という音を先鋭化したというか、拡大解釈していろんな表現の根本に据えていったんだと思います。
──山中さんと悌二さんとしてはそこまで“ピッ”を拡大していこうとは考えていなかった?
山中 僕らにとっては記号音……パフォーマーが動くきっかけになるようなサインだったから。その後、「pH」「S/N」でビートを刻むものとして使い始めましたけどね。
●ダムタイプの真骨頂である映像と音の同期
──池田さんにツアーの音響オペレートを任せるころには機材がだいぶ進化していましたよね? 映像と音楽が同期するようなシステムを構築できたのはいつからだったのでしょう?
山中 「S/N」からですね。「pH」では音楽はDATというデジタルのテープから送出していましたが、映像はまだ16mmフィルムを使っていました……本番中フィルムが燃えたこともありましたよ(笑)。
──では「pH」のときはまだ手動で映像と音楽を合わせていた?
山中 はい。DATウォークマンを3台とサンプラー、そしてYAMAHA DX7を使って。「pH」の舞台は観客が上から見下ろす構造なので、どうしてもブースが狭くなってしまって、そこにDATウォークマンとDX7とサンプラー、そして16chのミキサーやエフェクターを置いたらもうパンパン。それなのにシーンごとにエコーやリバーブを細かく調整しなくてはいけなかったりするので、いっぱいいっぱいでした。
──では「S/N」で映像と音声が同期できるようになったのは革命的だったんですね。
山中 はい。AKAI PROFESSIONAL MPC60IIというシーケンサーとサンプラーが一緒になったものが、映像と同期するようなシステムを組んだんです。映像の方にSMPTEという同期信号を入れておいて、MPC60IIはその同期信号を受け取ることができるスレーブ状態にし、映像の再生が始まったらMPC60IIのシーケーンサーが自動的に走り出して、音源として用意したE-MU MorpheusとROLAND JV-2080にMIDIの演奏情報が伝わって演奏が始まる。なので本番中の僕の作業はそれぞれの音源の音をミックスしつつ、パフォーマーが倒れ込むときに鳴る“ドーン”という音をMPC60IIのパッドでたたくことでしたね。
──「OR」の公演になると、ハードディスク・レコーダーが導入されていましたよね?
山中 ええ、AKAI PROFESSIONAL DR16という16trのものです。同期システムとしては「S/N」のときと同じで映像のスレーブとして使っていました。
──ハードディスク・レコーダーを導入してからは、MPC60IIのときのようなMIDIで各音源を鳴らすやり方ではなく、録音された音楽を流すようになったのですか?
山中 主に亮司君の音がハードディスク・レコーダーから再生され、僕が作った曲では変わらずMPC60IIを使っていました。「OR」のころはさすがに予算も潤沢で、機材をたくさん持っていってもOKだし、ブースも広くなって2人で入っても大丈夫。今のダムタイプってブースの方が広いでしょ? この前も新作のリハに行ったらブースの人の方が多い……ブースに12人くらい居て、舞台の人が4人くらい(笑)。
──どんどん舞台に立つ人が少なくなってくるっていう不思議な集団ですよね(笑)。
山中 もうちょっと増えた方がいいんちゃうかな。
──その新作に山中さんも参加されるのですか?
山中 します。もう、スンマセン、新人ですという感じで(笑)。(古舘)健ちゃんとか(原)摩利彦君が僕のためにブースの真ん中の席をばーんと空けてくれているけど、無理無理~と(笑)。
──音楽家としての参加ですよね?
山中 ですね。若いスタッフには無い何かが出せて、その結果新しい表現ができたらいいなと。でも、いい機会だからコンセプトから参加できたらと思ってます。僕らができる最上のものって何ぞやということをお互い突き詰めたい。ダムタイプが一番得意なのはコンポジション……コンポーズすることなんで、そのコンセプトのもと各メンバーが得意とするものを出していくといい。僕自身、新作をとても楽しみにしています。
Day 3 -「pH」 after talk with 藤本隆行 (2019年11月27日)

●コピー機のように舞台を走査する2つのトラス
──まず、藤本さんがダムタイプで何をしてる人かをご存じない方もいらっしゃると思いますので、その辺りのお話からお願いいたします。
藤本 えーっと、ダムタイプって昔から役割を縦割りしてないグループで、今の僕は照明を主にやっていますが、「pH」のときは舞台セットの中で動いている上下2つのトラスを制御する役だったんです。そういう役割分担は上演の際には決まりますけど、制作中はみんなで話をしながらっていうのがダムタイプで、「pH」のときは本当にメンバーの役割がフラットでしたね。
──メンバーそれぞれが時と場合によって全く違う作業をする?
藤本 そうです。例えば高谷(史郎)は建築をやってたので図面が引けるから、「pH」のセットは全部彼が設計しています。高谷は図面を引いただけでなく部品の仕様を書いて発注までしていますね。で、届いた部品をもとにメンバー全員でセットを組み立てます。次の公演場所に移動する際にはバラさなくちゃいけないから、公演ごとに組み立て直す……1回の公演で1,000個くらいのネジを締めるのかな(笑)。ダムタイプのパフォーマンスはそういうところから始まるんです。
──今回、東京都現代美術館で開催されている個展「ダムタイプ|アクション+リフレクション」では、その「pH」のセットがインスタレーション・バージョンとして再現されていました。設営を見学させてもらったんですが、原摩利彦さん、古館健さん、濱哲史さんという新世代のダムタイプの音楽家が組み立てていましたね。
藤本 はい、みんな何でもするんです(笑)。
──藤本さんがダムタイプに参加するようになった経緯を伺いたいのですが、創設時からのメンバーなのですか?
藤本 ちょっと違うんですよね。ダムタイプって京都芸大(京都市立芸術大学)の劇団“座・カルマ”がもとになっていて、そこから“ダムタイプシアター”っていうのになるんです。そのときの主なメンバーは古橋(悌二)、高谷、小山田(徹)。僕は学年としては彼らより1年上で、大学に行きつつ大道具さんのアルバイトをやっていました。卒業してからはフリーの大道具さんになって絵を書いてたんですが、まあ元々彼らとは知り合いだったし、大道具ができるからって手伝うようになって、「036-Pleasure Life」のときから参加しました。
──山中さんによると「036-Pleasure Life」がダムタイプという名義になった最初の作品ということでした。
藤本 そうですね。
──「pH」の舞台構造を説明していただきたいのですが、セットが組まれた舞台を観客は上から見下ろす形だったのですか?
藤本 そうですね。動くトラスが上と下の2つあって、スキャナーみたいに……当時はコピーマシンって言ってたんですけど、それぞれが動く。
──上下のトラスで役割の違いはあるのですか?
藤本 上のトラスは映像を投影する装置を積んでいて、下のトラスはパフォーマーにとって物理的な障害物になるもの、という役割ですね。下のトラスには蛍光灯とスピーカーも付いています。最初の“ポーン”という音とかはそこから出ていますし、あと「酒とバラの日々」とかの音楽も下のトラスのスピーカーから鳴らしているので、トラスが動くと音源も動く。
──上のトラスにはどんなの映像機器が設置されていたのですか?
藤本 スライドプロジェクターです。ビデオプロジェクターはまだ高くて買えなかったので、スライドプロジェクターを6台積んで、2台ずつをペアにしてディゾルブで映像を切り替えていくようにしました。
──2台のスライドプロジェクターを同じ面に向けて投射している?
藤本 はい、一度鏡に当ててて真下に落として1つの画面を共有するようにしています。6台のスライドプロジェクターですから、都合3画面がそれでできましたね。ちなみに奥の壁に投影している映像はトラスからではなく、別のところに設置した16mmの映写機を使っていました。映像素材自体はビデオ……確かUマチックで作ったものなんですが、当時、ビデオプロジェクターで大きく投影できるものがなかったから、わざわざテレシネで16mmフィルムに変換して映写しています。16mmフィルムだったら世界中に映写機がありましたからね。
●上下のトラスの動きをコンピューターでプログラム
──藤本さんが担当したという2つのトラスの動きは、具体的にはどのような仕組みになっていたのですか?
藤本 トラスそのものにモーターが内蔵されているわけじゃなくて、端にモーターがあって、ワイアーで引っ張っていたんです。最初の頃はうまくいかなくてよく止まっていました。みんな芸大生なんで工学系じゃない……動力をどうやって伝えるといいかなんて分からないんですよ。外れたワイアーを取り付けようとして手が血まみれになってるやつがいたりして大変でしたね(笑)。
──ワイアーの制御はどのように?
藤本 リモートで行えるようにしていました。最初期のコントローラーはぼろぼろの缶詰めみたいな箱でした。トラスを動かすためのデータを入れるバンクですね。モーターに1つパルスが入るとある角度分だけ回るようになっていて、例えば1,000パルス入れると結果として1mワイアーが引っ張られるとか。なので10mトラスを動かしたいなと思ったら、このバンクのダイアルを回して10,000って数値を入れて、スピードも入れて、行けって命令するとトラスが指定した距離を指定したスピードで動く。設定を間違えると机にぶつかったりするんで結構怖くて、誰か殺すんじゃないかと思ってました(笑)。上のトラスは重たいですから落ちると死ぬし、下は下でパフォーマーに当たるので危ない。
──緊急停止とかはできないのですか?
藤本 確かそういうボタンを付けてたと思います。でも、それを使って緊急停止すると、その後のパフォーマンスをどうするっていう話になりますしね……。
──大変だったんですね。
藤本 ええ。初演とかその前のテストのときはこの初期型コントローラーでやっていたんですけど、これじゃ絶対無理だなって。そもそも上のトラスと下のトラスとが別のコントローラーで、それぞれ別の人がやっているから意思疎通をしなければいけないとか、血を吐くかと思いました。
──それで違うコントローラーを用意した?
藤本 はい、コンピューター制御になったんです。まあ、コンピューターといってもMacでもWindowsでもなく、富士通FM-7というBasicが動くマシンでした。トラスの動きをプログラムで書いておいて、“GO”ボタンを押せば、書いた順番で動く。とても画期的で、それ以降2つのトラスを1人で制御できるようになりました。
──工学系のメンバーがいなかったというのに、なぜそんなことまでできるようになったのですか?
藤本 中川(典俊)君という僕の高校の後輩が作ってくれたんです。電子工作に強くて「036-Pleasure Life」でもビデオ信号のディバイダーを作ってくれました。ダムタイプのメンバーではないんですけど、影のメンバー的な……近くに住んでいなかったので、電話とかで話してファクスで図面を送ってきたりとか、そういう時代です。
──先程説明していただいた6台のスライドプロジェクターの制御は、トラスの制御とはまた別系統なのですか?
藤本 はい、それはDATATON社のPaxっていうハードとソフトが一緒になったスライドプロジェクターの制御機器があって、日本だとエルモ社が代理店になっていたのでシステムを用意してもらいました。制御システム自体も上のトラスに積んでいましたね。
──しかし、手作りのシステムが多かったことに驚かされます。
藤本 そうですよね(笑)。モーター屋さんに行って話を聞いて、ACサーボモーターという、負荷が掛かってもトルクを調節すれば同じスピードで動くモーターを選んで、これだったらコンピューターでも制御できるじゃないかとか、そういうことの積み重ねですよね。できそうな感じがするからどんどんやっていく。
●劇場の設備を使わずすべてを自力で行う時代
──そもそも舞台装置としてコピー機のようなものを作ろうとしたのはなぜだったのですか?
藤本 それは作品のコンセプトですね。「pH」を作っていたのは1980年代の終わりくらいで、ベルリンの壁が壊れる直前。ツアーをしている最中に湾岸戦争が始まったので、戦車が出てくるシーンを付け加えたのを覚えています。その頃って消費社会がずっと続いている感じで、新しいものもなければ世界もずっと変わらないっていうイメージだった。それとコピー機がリンクした感じですね。あと「pH」というタイトルも酸性とアルカリ性の間をずっと動いているっていうイメージ。舞台では“phase”ていう言葉も使っていました。そして地獄……インフェルノやリンボーと天国の間を動くというイメージもありましたね。
──昨日、山中さんから伺った話では、「036-Pleasure Life」のような上から見下ろす構造のパフォーマンスだとツアーに出るのが大変なので、普通の劇場で公演できるように「Pleasure Life」を作ったということでしたが、また上から見下ろすような舞台に戻ってしまったのはなぜですか?
藤本 「Pleasure Life」をやってみて、やっぱり無理だと思ったんですよ。「Pleasure Life」では劇場に用意されている照明などの舞台機構をほとんど使わなかったというのもあって、すごく窮屈だったんです。そもそもダムタイプのメンバーはみんな劇場のことをほとんど知らない……僕は大道具の人でしたから一応は知ってましたけど、ほかのメンバーは知らなかった。劇場付きの照明さんってすぐ怒るから怖いし、僕らが何かやろうとするとすぐに“それは無理だ”って言う。なので、元々芸大生っていうのもあるでしょうけど、舞台機構に則ったものを作るよりゼロから作る方がいいっていう感じで、「pH」ではまた劇場の設備を使わずに全部自分たちでやろうということになったんです。照明についても、舞台用の照明装置でなく店舗用や蛍光灯、ナトリウム灯を使って、それらをモーター制御できるようにしたり。そういうのがダムタイプっぽさの1つになったのは確かですけどね。
──劇場の設備を使わないやり方で海外ツアーを回るのは大変だったのでは?
藤本 はい、とっても(笑)。全部の荷物合わせると2tぐらいになった。それをでかい木箱2つに入れてコロを付けて……輸送してる間はトラックが運んでくれるからいいんですが、劇場に着いたらぽーんと出され、時には搬入口から離れたところに放り出されるので、ピラミッドを作る奴隷みたいに舗装のない道をゴロゴロ押して運ぶとか。
──ツアーの先々でそれを?
藤本 そうなんですよ。それで結局「S/N」のときは劇場の舞台機構を使ってでも、たくさん回りたいって言うか、ちゃんとツアーをしようっていうことになりました。仕方ないから照明も覚えなきゃって。
──それで藤本さんも照明をやるようになった?
藤本 はい、そうなんです。
●パフォーマンス全体を規定するダイヤグラム
──記録映像を観ると「pH」は今でも新鮮な驚きを感じる舞台です。生で見たかったですね。
藤本 生でやってる方は大変でしたけどね(笑)。
──山中さんも「pH」が一番大変だったとおっしゃってました(笑)。
藤本 記録映像では見えない、分かりにくいところがいっぱいあるんですけど、例えば“ドン”って音がしてテニスボールが投げ込まれるんですが、あれはオペレーションブースの端にピッチングマシンが置いてあって、そのボタンを押して出すんです。
──誰が押すのですか?
藤本 照明を担当していた泊(博雅)君が押してるんですけど、何分何秒で押すみたいなことが決まっていましたね。
──つまり「pH」のパフォーマンスは、全体で時間管理がされていたということですか?
藤本 はい。上と下のバーの動きが鉄道のダイヤグラムみたいに表示されたものを用意していました。斜めの角度がきつければ動きが速い。
──パフォーマーの方々はそのダイヤグラムを意識してやっている?
藤本 そうですね、でないとバーに当たって痛いので。
──秒数は誰かがカウントしてパフォーマーに伝えているのですか?
藤本 そんなことはしていないです。バーがこっちに行ってあっちに行っていうのを数えていました。まあ音楽も同期というか何となく合わせているからそれも目安に。
──そのダイヤグラムの中のどこかに、ピッチングマシンのスイッチを押すとか指示が書き込まれている?
藤本 そうですね。
──なぜ、そこまでしなくちゃいけないのですか?……っていうと変な質問ですが、普通の舞台や演劇をやってる人からすると、ダイヤグラムを組むとかって想像もつかないような世界だと思います。
藤本 こうやったらできるよっていうのを開発していくのが好きだったんでしょうね。とりあえずやったら動くし面白いなってやってる感じですよ。
──みんなそういうのが好きだった……と。
藤本 ですね。いろいろ考えるのが楽しかったんだと思いますよ。
──最近は何でもかんでもコンピューターで制御できてしまう……制御どころか映像も音楽もすべてコンピューターから出せるようになりました。楽しさが見いだしにくくなったりはしませんか?
藤本 いや、そんなことはないですね。例えば多くのコンピューターを使ってネットワーク組んでいると、分散的というかだれか1人のキューで動いたりしますよね……さっきのキューは照明が出したけども、次のキューは音響が出すとか。ネットワークで全部できたりするのって僕はすごく面白いと思うんです。僕は今、CYCLING’74 Max8でDMXの照明卓を制御していますが、それがOSC(Open Sound Control)経由でほかの人とつながっています。そういうネットワークが組めると、照明以外にも手が出せるようになり、表現の幅が広がってくる。自由になった部分も大きいと思いますね。
Day 4 -「S/N」 after talk with 藤本隆行 (2019年11月28日)
●音と同期するストロボとビデオプロジェクター
──「pH」で藤本さんは印象的な舞台装置であるトラスの制御担当だったとのことですが、「S/N」では何を担当されたのですか?
藤本 僕は現在、主に照明をやっているんですけども、ダムタイプのパフォーマンスで照明のオペレーションをしたのは「S/N」が初めてなんです。
──それまでに照明の心得は?
藤本 全然(笑)。
──昨日のお話ですと元々は大道具さんだった?
藤本 はい。芸大(京都市立芸術大学)在学中にアルバイトで大道具に行って……京都には花街があるから歌舞練場っていうのがあり、そういうところで学んでいたんです。でも照明は全然やってなかった。劇場の照明さんは怖い人が多かったですからね。もちろん、生命が掛かっている……何か落ちると死んでしまいますから、厳しくて当たり前の世界なんですけど、本当に危ないから怒っているのか、自分のポジションを守るために怒っているのか分からなかったので、なるべく関わりたくないなと思ってたんです。まあ、大道具だって変わりませんが。
──藤本さんがやる前のダムタイプはどなたが照明を?
藤本 それまでは高谷(史郎)がやってましたね。
──では、なぜ「S/N」で藤本さんが照明をやることに?
藤本 ほかにいなかったからです。「S/N」で高谷はCG/映像をやるっていう話になって、じゃあ僕が照明をやろうと。大道具をやってたので舞台の人に対する注意事項みたいなことが分かっていたので。
──「S/N」の照明と言えばやはりストロボが印象的です。今回、記録映像を見てあらためてものすごくたくさん光っているなと。ストロボを多用するというプランはどういうところから出てきたのですか?
藤本 どうなんでしょうね……僕は「S/N」のときはプランは書いてないんですよ。高谷がプランを書いたんです。ストロボをダムタイプの舞台で使ったのはこの時が初めてだったと思います。
──音と連動して光っているように見えたのですが、何か同期システムを入れたのでしょうか?
藤本 「S/N」では映像と照明とが同期するようなシステムを入れていない時期ですが、ストロボについては写真撮影用のものを使っていたので、カメラのシャッターを切ると光らせることができるような仕組みを利用して音と連動させています。それとは別に舞台照明用のストロボも使っていて、2灯は壁の両側に置いて上の通路を、それ以外は壁裏からホリゾント幕に当たって光るようにしていました。
──照明のオペレーションは普通にブースで行っていたのですか?
藤本 はい、照明卓経由で行っていました。「pH」の頃は本当に舞台のシステムを使いたくないっていうか、やっぱりちょっと違うよねっていう話をしてたんですけど、「S/N」は多くのところを回りたいっていう欲が出てきたというか、「pH」の舞台があまりにも大変だったから、効率良く回していくには舞台設備をちゃんと使った方がいいんじゃないかと。
──劇場に元々あるシステムを使うということですね。
藤本 そうです。その方が作品としても成立しやすいじゃないかって。
──それで劇場備え付けの照明卓も使うようになったわけですね。
藤本 はい。でも、それとは別にいろいろな制御マシンを作ったりもしています。例えば「S/N」からやっと液晶プロジェクターを使うんです……買えるような価格帯になったのでね。でも液晶なので何も映ってない時も明るい。暗転してる時に四角い画面が見えてしまうんですね。これはかっこ悪いよねという話になって、アルミ板とモーターを組み合わせて、映像を投影したいときだけに開くシャッターを自作して、レンズの前に取り付けました。
──「pH」までの映像はスライドと16mmフィルムの映写でしたが、「S/N」では全部ビデオに切り替わった?
藤本 いや、依然としてスライドは使っています。エンディング近くでパフォーマーが服を脱いでいくシーンがありますよね? あのとき舞台を縦の白い光が走査していくように動きますが、あれはスライド映写機が出している光なんですよ。あれをビデオでやると地が締まらないっていうか周りが明るくなってしまう。ピシっと光を見せたい場合はスライドの方が良かったですね。たくさん表示されるテキストも読みやすいからスライドを使っていました。
──縦の白い光が動いていくのは、どのような仕組みだったのですか?
藤本 スライドプロジェクターの前に鏡を置いて、その鏡を回しているんです。一応モーターで動かしてますけどめちゃくちゃアナログですよ。
──そういう意味で「S/N」はアナログ機材からコンピューター時代になっていく端境期の作品?
藤本 そうですね。やっとCGが作れるようになりましたし。
──CGはどのシーンで使われていたのですか?
藤本 AIDS治療の薬品……AZTのカプセルがくるくる回るシーンとかですね。
──タイプライターを打つ音に合わせて文字が1つずつ出てくる……“Conspiracy of Sience”などの文字もCGですか?
藤本 あれもCGっていうのかな……文字の画像を編集した映像と音が合うように、SMPTEっていう規格で映像と音声とを同期させています。
●全部がシステムで動いたら人間がノレない
──「S/N」の舞台セットですが、手前に平場の舞台があって奥に映像が投影される壁があり、その壁の上にも通路的な舞台があるという2階建てになっていました。上の舞台からパフォーマーがホリゾントの方へ倒れ込むシーンがとても印象的ですが、後ろはどういう構造になっていたのでしょうか?
藤本 後ろは段差はあまりなくて、そこにクッションとタイヤチューブを置き、倒れ込んでも怪我をしないようになっていました。何でタイヤかっていうと空気を抜くと持ち運びやすくなるので。「pH」のときの2tにもなるようなセットがもう嫌だったので、タイヤだと空気を抜けば軽いし場所も取らない(笑)。
──上の舞台が“動く歩道”のようにも見えましたが、何かそういう機構が組み込まれていたのですか?
藤本 いや、違います。今でもあそこがベルトコンベアだって信じてる人がいますけど、普通の舞台で、左右に動くのはコロを付けた台車を上手と下手で人力で引っ張っているから。ああいうのを電動にしたらかえって危ないんです。人間がやってるから倒れそうになったら止められる。
──後半でパフォーマーが走り続けるシーンを見て、ベルトコンベアというかトレッドミルみたいなものが組み込まれているのかと思っていました……。
藤本 いや、あれは何も無いところで空走りをしてる(笑)……パフォーマーたちの練習の成果ですね。そんなにハイテクノロジーじゃなくてもあれぐらいのことはできる。今でもそうですけど、全部がシステムで動いちゃったら人間がノレないじゃないですか。人間が一番アナログなので、そこは拾えるようにしとかないと。すべてが同期しちゃうとタイムラインが決まってしまうので、それに人間が合わせるしかなくなる。なので同期している部分と手で動かせる部分っていうのがどちらもあるようにしておいて、その組み合わせをやることによって人間がノレる、みたいなことを考えていました。
●初演のアデレードで初めて全貌が露わに
──今回、ダムタイプのパフォーマンス作品上映会を開催していて、そもそもよくこれだけの記録映像が残っているのだなと感心しました。
藤本 そうですね、古橋はビデオ映像作家でしたから、彼が全部撮って編集もしていたんですけど、当然撮っておかなきゃという意識があったんでしょうね。撮影機材がまだまだ高い時代でしたけど、芸大にはUマチックの機材があって、編集室もあったっていうのが大きかったですね。
──今日、改めて「S/N」をご覧になっていかがでしたか?
藤本 しんみりしましたね……。“Conspiracy of Science”って言葉を見ると、フェイクニュースばかりの現代に通じているっていうか、本当に状況が変わってない。HIVの治療薬はすごく良くなってますけど、取り巻く環境は変わっていないっていうか、余計悪くなってるかもって思うとちょっと悔しいです。
──「S/N」はそれまで集団制作だったダムタイプとしては例外的に、古橋さんがリーダーシップをとった作品と聞いています。どんな作品になるかメンバー間での共有はされていたのでしょうか?
藤本 もちろん、こういう内容を作ろうっていうのはみんなで散々話をして構築していました。初演はオーストラリアのアデレードというのは決まっていたんですけど、内容的にいきなり初演というのも難しいということで、セミナーショーを開催したりして探り探り始めたんです。でも、結局、初演のアデレードまで全体の時間軸が分かってたのは古橋だけだったんですよ。あとは多分、だれひとりとして全体像が分からなかった。高谷は古橋と映像を作っていたからある程度分かっていたかもしれないし、山中も古橋と音楽を作っていたから少し分かっていたかもしれないけど、僕は照明ですから、アデレードのリハで“うわーっ、こんなになるんや”って初めて分かった。シーンごと、パーツでは見ているんですけど全体像が分からなかったんです。
──最初の方のストロボが多用される派手なシーケンスも、初演のアデレードで初めてみんなが知った?
藤本 そうです。でも、古橋の頭の中では整理されていたんでしょうね。本当に本人が望んでと言うか、作りたくて作りたくて……作らなきゃいけないという気持でやってましたからね。
──ほかのダムタイプ作品と比べ、「S/N」は言葉の情報量が多いですよね。今回の上映会で何回も観ることで、やっとそれらを少し受け止めることができました。そういう意味では多くの人が何度でも見返すことができるようにすべきだと思いました。何度見ても飽きないし、気づきがあります。
藤本 久しぶりに見て、僕もああこんなやったなと思いました。ダムタイプって本当は言葉を使わないっていうところから始まってるんですけども、「S/N」に関してはテキストっていうか言葉の力借りないとできないよねっていうのはありました。まあ、タイプに合わせて字が出ると単純にかっこ良かったからっていうのもありますけどね(笑)。
Day 5 -「OR」 after talk with 上芝智裕 (2019年11月29日)

●「pH」の舞台で実装したコンピューター制御
──上芝さんがダムタイプに加わったのはいつですか?
上芝 1990年~1991年くらいですね。学生のときにお客さんとして観に行ったのがダムタイプ初体験で、年代的にも創設メンバーは先輩たちです。
──創設メンバーは京都市立芸術大学の方々でしたが、上芝さんも同じ大学だったのですか?
上芝 全然違うんです。僕は京都芸術短期大学……今は京都造形芸術大学っていうところで、そこでコンピューターグラフィックス(CG)を勉強していました。
──その当時CGを学んでいたというのは、かなり早かったのでは?
上芝 そうですね。僕の師匠が幸村真佐男さんっていう、1968年……僕が生まれたころからCTG(Comupter Technique Group)っていうグループでCGをやっていた方だったんです。CGと言っても、当時はプロッターを使ってペンを動かしてプリントするような世界でした。その幸村先生の助手って言うか、機材とかを管理する人が、当時のダムタイプでプログラミング周りやデザインをやっていた穂積(幸弘)さんだったんです。
──それが縁でダムタイプを観に行くように?
上芝 はい。最初に観たのが「pH」だったんですが、ものすごい衝撃で……もう大ファンになって、ファンが高じてお手伝いさせていただくようになりました。
──創設メンバーではなく、後からダムタイプに加わった方は元々ファンだったというケースが多いですよね。それこそ池田亮司さんもそうだと伺ってます。
上芝 ええ。僕と池田さんは同じ学年なんですよ。
──ファンだからといってダムタイプは簡単に参加できるグループではないと思いますが、どうやって加入したのですか?
上芝 偶然が幾つか重なり合ったんです。僕が学生の時に参加したグループ展の開催場所が、たまたまダムタイプの事務所の向かいのギャラリーだったんです。それで高谷(史郎)さんや(古橋)悌二さんが見に来てくれて、お話する機会があったというのが1つ。その後、穂積さんがツアーに出るのは大変だからダムタイプをやめたいって言ってるのを聞いて……僕はそのころ大学を卒業して就職していたんですけど、当時はバブルだったんで会社で企画書を書いたんですよ……“ダムタイプの手伝いをすることは仕事にも有効だ”みたいな(笑)。
──そんな企画が通るような会社だったんですか(笑)。
上芝 機械を作る会社だったんですけど、その製品をプロモーションをするための映像を作る部門に居たので、ダムタイプは映像も関係しているからその仕事にかかわるのは有意義だと(笑)。それで1年の1/3くらいはダムタイプのツアーに付いていくようになったんです。
──バブルとはいえ、新卒の社員がそんな企画書を書いて通るだなんて……今だったら考えられない話ですね。
上芝 いやいや、それくらいバブルの時はイケイケだったじゃないですか。ただし、1993年くらいにバブルが弾けた瞬間、即リストラされました……コイツは何をやってるんだみたいな感じになって(笑)。
──ダムタイプに加入されたときは、穂積さんのやっていた仕事を引き継いだ形だったのですか?
上芝 穂積さんはダムタイプでいろいろな仕事をされていたので、全部は引き継げなかったですね。僕はプログラミングができた……と言っても、当時まだWindowsは無いですし、Macはありましたけど、MacもCGソフトも高かったですから買えなかった。僕が使っていたのはNECのPC-98っていうシリーズで、C言語とかPascalでプログラムを書いていました。その知識を生かして「pH」のトラスをコンピューター制御できるようにしたんです。キーボードをポンとたたいたら、そこから先は自動である程度進むっていうものですね。
──実際の「pH」の舞台でもPC-98が使われていたのですか?
上芝 いや、現場ではTOSHIBAのJ-3100……Dynabookって呼ばれたラップトップを使っていました。
●「S/N」「OR」を特徴付けたマルチスクリーン
──今のお話をうかがうと、上芝さんはダムタイプのコンピューター化に貢献したということですか?
上芝 穂積さんがやりかけてたのを引き継ぎつつですね。その後は映像のマルチスクリーン化を担当しました。例えば「S/N」の映像は4画面で、今日観ていただいた「OR」は3画面。それら複数の画面があたかも1つの映像として投影されるようなプログラミングをしました。
──具体的にはどうやっているのですか?
上芝 「OR」を例に採りますと、半円形の湾曲したスクリーンが舞台の背景としてあって、そこに3基のプロジェクターで1/3ずつ映像を投影しているんです。当時、そういうマルチ画面をやろうと思うとものすごいお金がかかったんですけど、いろいろ工夫してコンシューマーレベルの機材でやりました。具体的にはHi8というSONYが提唱したビデオ規格のビデオデッキを使っています。Hi8のビデオデッキにはリモコン端子が付いていて、外部のリモコンで再生とか停止ができるんですが、そのリモコン端子にSONYのVboxという機械をつなぐと、コンピューターから再生や停止の命令を送ることができた。しかも、Vboxは複数のHi8デッキにつなぐことができたので、それらを同時に再生できる……つまり3台のビデオデッキを同期させることができたんです。
──そのVboxに命令を送るためのコンピューターのプログラミングを上芝さんが書いていた?
上芝 そうです。HyperCardっていうソフトを使ってコントロールしていました。
──HyperCardって、MacintoshにバンドルされていたAPPLE純正のソフトのことですか?
上芝 そうです。今だったらFileMakerみたいなデータベース・ソフトと言っていいんでしょうか……カード型のデータベースで、その中にちょっとプログラムできるような機能があったのでそれを使っていました。
──HyperCardからVboxに“再生しろ”っていう命令を送ると、3台のビデオデッキが再生を始め、半円状のスクリーンに投影が始まる……ということですね。それぞれのデッキで再生ポイントやスピードがずれたりはしなかったんですか?
上芝 ずれないんですよ。いろいろ実験したんですが1フレームもずれませんでした。なので「S/N」そして「OR」の公演でのマルチ画面は全部このシステムで投影しました。
──そのマルチスクリーンの映像と音楽とが完璧に同期していたわけですよね?
上芝 はい。「S/N」のときに既に映像と音楽が同期するようになりましたが、「OR」からは照明も同期できるようになりました。「OR」から音楽の再生にAKAI PROFESSIONALのDR16というハードディスク・レコーダーを導入したのですが、照明はそこからSMPTE信号をもらって、それこそストロボの発光をぴたりとシーンに合わせることができるようになりました。「S/N」のときのストロボは、撮影用の機材を使ってそこにオーディオ信号を入れることで同期させていたんですが、やはりアナログのオーディオ信号なのでフレーム精度は出なかった。でも「OR」ではそれがぴたりと合う。カメラのシャッター音がバシャって鳴って、それに合わせてストロボが光るシーンが3カ所くらいあるんですけど、今日、観ていて気づいたのは、最後のシーンだけ光った瞬間にワンフレームだけ映像が出るっていう演出。ものすごくマニアックな話ですけど(笑)、一応そこまでタイミングを合わせることができるようなっていたんです。
──同期システムについて確認したいのですが、山中さんからマスターは映像で、音楽はスレーブと伺いました。照明はさらにその音楽のスレーブということですか?
上芝 はい、マスターは映像で、ビデオテープの音声トラックにSMPTE信号が入っています。その信号をもとに音楽が入っているDR16が同期して動き、さらにDR16から出力されるSMPTE信号にストロボが同期していたと思います。ダムタイプってある意味素人っぽいというか、みんなその道のプロじゃないんですね。だから、その頃の作り方を僕なりにまとめると、基本は超ローテク、そしてブリコラージュ。あるものをどうにかやりくりして何とかやっちゃう。めっちゃ安い機材でいかに作り上げるかっていうことをやってたんです。
●ポータブル編集機の登場が生み出した際限ない映像編集
──「OR」での上芝さんは映像送出のプログラミングを担当していたという理解でよろしいですか?
上芝 プログラミングだけでなく、映像制作とか映像編集もお手伝いさせてもらってましたね。
──ダムタイプは古橋さんが元々映像作家で、高谷さんも映像を作るようになり、そして上芝さんも作っていた?
上芝 泊(博雅)さんも作っていました……彼は大学で映像制作も教えてましたからね。
──「OR」のころの映像編集はどのように行っていたのですか?
上芝 出たばかりのデジタルビデオの編集機を使っていました。PANASONICが開発したDVC PRO規格のAJ-LT75というモデルで、2本のビデオテープを入れて、ジョグ/シャトルダイアルで両方のビデオの頭出しをしながら、カチャカチャとつないで編集していくものです。それまでの編集機と比べて作業が格段に楽になったんですけど、ポータブルだったので世界中どこでも編集できるようになってしまったんです。「S/N」までは映像編集を日本の編集スタジオで全部やり切るしかなくて、編集が全部終わってからツアーに出て上演する。だから日本から出たらもう編集作業は無かった。でも、ポータブルなビデオ編集機が出たおかげで、ツアー中のホテルの部屋で、それこそ公演の直前まで編集できるようになっちゃったんです。
──ツアーの途中で映像を変えることさえできるように?
上芝 そうなんですよ(笑)。この後さらにラップトップで音も映像も作れるようになってからは、もう本当にすべてが公演中にいじれるっていう。
──それは善しあしですね……。
上芝 そうなんです。便利にはなったけれども仕事は無限に続く……無限地獄になりました(笑)。
●古橋悌二亡き後の作品制作
──「OR」は古橋さんが亡くなられた後ということもあり、制作が大変だったと思います。それこそ「S/N」を最後にダムタイプを離れたメンバーもいたわけですが、上芝さんはどういう気持ちで「OR」に参加されたんですか?
上芝 参加したいという強い気持ちがありましたね。なんでだろう……池田さんもいるから一緒にやろう、みたいな感じだったんじゃないですかね。
──ダムタイプのクリエイションの現場がどんなものなのか想像が付かない……あまり和気あいあいした感じではないのではと勝手に思うのですが、本当のところどんな感じなのでしょうか?
上芝 いや、ギスギスしてはいないですよ。この間も高谷さんと東京都現代美術館での個展のオープニングのときに話したんですけど、“いつも爆笑の連続やったよね”って。僕も笑って暮らしてた……楽しいという記憶ばかりですね。
──山中さんは古橋さんと喧嘩ばっかりしていたとおっしゃってましたが。
上芝 それは悌二さんが無茶な要求をどんどん出して、山中さんがそれを形に落としこむ作業が大変だったからだと思います。
──上芝さんは「pH」のツアー途中からダムタイプに参加されて、「S/N」はフルでコミットされて、「OR」もすべて参加されたのですか?
上芝 いや、「OR」は1997年のアルス・エレクトロニカまでじゃないですかね。その後、離れることになりました。
──差し支えなければ離れた理由は?
上芝 結婚したからですかね(笑)。もう付いていけなくなった……やっぱりツアーについていくのが無理になってきたってことじゃないですか。
──ダムタイプを離れてからもさまざまな活動をされていますよね?
上芝 その後、池田さんがすごく有名になっていって、僕も音楽を作りたいなって思うようになったんです。それでダムタイプの今回の個展や新作のチラシをデザインしてる南(琢也)君と2人で1999年にSoftpadというグループを作って活動を始めました。自分はもともとビジュアルの人なんですけど、ビジュアル作品って音があるから作れる部分があるので、ビジュアルを付けるための音楽を作り始めたんです。最近はデザイン寄りのビジュアル作品を作っていて、サウンドアーティストの藤本由紀夫さんたちと一緒に音と文字……デザインに関わる一番の大事な文字のところをテーマにしたphono/graphっていうプロジェクトをやっていますね。
Day 6 -「memorandum」 after talk with 高谷史郎 (2019年11月30日)

●ノンリニアの映像編集による制作環境の変化
──改めて「memorandum」をご覧になっていかがでしたか?
高谷 懐かしかったですね……映像的にかなり古い機材でやってたんだなぁと思いながら観ていました。
──「memorandum」のころはどんな機材を使って制作していたのでしょう? もうパソコンで映像を作る時代に入っていたのですか?
高谷 まだパソコンでは作ってないですね。「OR」のときにテープベースのデジタル編集機だったのが、「memorandum」からはノンリニアの編集機になりました。Trinityっていうコンピューターベースの編集機なんですが、今のADOBE Premiereみたいなものじゃなくて、専用のハードウェアをWindowsでコントロールする感じのシステム。素材の映像をテープからデジタルでハードディスクに取り込んで、拡大したりとかスピードを変えたりして出力するものです。1999年に坂本龍一さんのオペラ「LIFE」に参加したときに導入した機材で、「LIFE」の本編はデジタルベータカムを使って編集も編集スタジオでやったんですけど、サンプルっていうか、こういう映像を出そうっていうのを作るために使いました。
──“ノンリニア”っていう言葉自体が今の若い方には分からないかもしれません。ノンリニアじゃない……つまりリニアのころの映像編集はすべて実時間がかかったのですよね?
高谷 そうです。リニアのころは映像に数字のグラフィックを重ねようとしたら、1つのビデオデッキに基になる映像のテープを入れ、もう1つのビデオデッキに数字の映像のテープを入れ、それぞれを再生しながらビデオミキサーでミックスして別のビデオデッキに実時間かけて録っていく(笑)。昔はそういうやり方しかなかったんです。
──それがTrinityというシステムを入れたことで時間が劇的に短縮し、表現力もアップした?
高谷 そうですね。あとデッキの数も減らすことができました。
──昨日、上芝さんから「OR」のときから映像と音楽と照明がすべて同期するようになったと伺いましたが、「memorandum」の同期システムは「OR」と同じですか?
高谷 ほとんど同じです。「memorandum」は4面のマルチスクリーンなので、4台のビデオデッキがあって、4本のビデオテープのうちの1本か2本にSMPTEという同期用のタイムコードを入れ、コンピューターからSONYのVboxというビデオデッキを制御できる機械に再生コマンドを送ると、映像が再生され、タイムコードを受けた音と照明の機材も同期して走る。今からすると簡単なことなんですけど、当時としては音も映像も照明も全部同期できるっていうのが面白かったですね。
──全部が同期するシステムを組むと、本番中はあまりオペレートすることがなくなるのですか?
高谷 いや、パフォーマンス中ずっと同期が走っているわけではなく、シーンごとにスタート/ストップがあるんです。例えば「memorandum」で競泳選手の格好をしたパフォーマーがプールに飛び込むようなシーンがありますが、飛び込むタイミングに合わせてスクリーン裏を照らしていた照明が落ち、ホワイトノイズが爆音で鳴り、プロジェクターのシャッターが開いて4面映像の投影が始まる……となるんですが、僕がぴったりのタイミングで再生ボタンを押さないと間抜けな感じに……音も映像も出なくて、パフォーマーが飛び込んだ後に舞台に着地した“ドテ”っていう音だけが聞こえたりしてすべてが終わってしまう(笑)。
──それは責任重大ですね(笑)。
高谷 しかも、ビデオテープなので再生コマンドを送ってもすぐには再生されないんです。コマンドが送られるとプリロードされているテープが回り、タイムコードが出力されてそれに引っかかってやっと音が鳴って照明も変わるわけですから、若干のタイムラグがあるんですね。なのでパフォーマーの人と打ち合わせをして、手がこう動いたときに再生コマンドを送るとちょうどタイミングが合う、とか調整していましたが、さすがに本番中はいつもドキドキしていましたね(笑)。
──現在、コンピューターから直接、映像も音も出せる時代になり、そういうドキドキはなくなったと思いますが、同期させる喜びというか楽しさも無くなってしまったわけですよね?
高谷 そうですけど、だからと言って前に戻りたいかというと全く戻りたくないです(笑)。でも、今でも簡単なことは手で合わせた方が早かったりするんです。コンピューターからイーサーネット経由で信号を送るときに、例えば音に一瞬早く送らないとぴったり合わないとかがあって、それを合わせるために何回もトライするより、せーのって手でやっちゃった方が早い(笑)。
●テーマの記憶を想起させる半透明のスクリーン
──「memorandum」の舞台装置について伺いたいのですが、大きく使われていたのは半透明のスクリーンという理解でいいですか?
高谷 はい、PVCっていうポリ塩化ビニールのスクリーンで、磨りガラスのような半透明のものを使いました。3m幅のものを4枚つなげて横幅12mにして、舞台の中央辺りに置いていました。
──そのスクリーンに対して幾つものプロジェクターから映像を投影していた?
高谷 フロントに大きなプロジェクターが1台があって全体をカバーし、さらにホリゾントの方にリアプロジェクション用として4台。PVCは普通あまりリアプロ用途には使わないんです。観てもらってお分かりのようにプロジェクターのホットスポットというか、真ん中が明るくなって周辺がぼやける現象が強く出るんですね。「memorandum」では僕たちは“記憶”をテーマに作品を作っていたので、その磨りガラス的な特性……向こう側にいるパフォーマーがスクリーンに近寄ると輪郭がはっきりするし、遠のくとぼやけるっていうのが、記憶の構造に近いんじゃないかと思って採用したんです。
──ぼやけた映像が見えたり、急にパフォーマーの姿が現れたりして、とても不思議でした。
高谷 フロントのプロジェクターから出している映像をパフォーマーが居るところだけ黒味にして、パフォーマーに照明を当てると映像の中から人が現れたように見えるんです。
──逆にスクリーンの後ろに人がいても照明を当てない限りは見えない?
高谷 はい、フロントから投影している映像にマスキングされるから見えにくくなる。で、その見えなくなっている間にパフォーマーが出たり入ったり、近寄ったり遠のいたりしています。リアプロの投影をしている最中に入ると映像に影が出て、その影とさらにスクリーンの前にいるパフォーマーとの関係とかが、また記憶の構造を取り出してくれるかなと。
──とても効果的かつスタイリッシュですよね。
高谷 今日、改めて「memorandum」を観ていて思ったんですけど、同期がぴたりと合ってうれしいというのは体育会系の楽しみみたいなもので、それよりは何をどういうふうに表現したいのかっていうことが面白かったんだなと。自分にとって「memorandum」ってベルトルッチの映画なんですよ……「暗殺の森」とかをイメージしながら作っていました。「OR」のときはキューブリック。あ、でも「memorandum」にもキューブリックっぽいところがありますね……ホテルっぽい部屋の設定とか、殺人が起こるとか、ある一点に向かって時間がいろんな方向から進んでいって、それで終わるんだけど、実際は何も起こっていなかったとか。自分がパフォーマンスを作っていく上で映画はキーワードになっていると思いますね。
●18年ぶりに取り組むダムタイプ新作
──2020年3月には、ダムタイプとしては18年ぶりとなる新作が上演されるということですが、準備はどれくらい進んでいるのでしょうか?
高谷 京都ロームシアターの企画で始まって、1年以上前から準備をしています。毎月1回くらいメンバーが劇場に集まって、システムの実験をしたりもしますけど、それよりもコンセプチュアルな……例えば「memorandum」だったら記憶がテーマだったように、何をテーマにどういう素材を使うのかとか、そういう話を延々しています。“ダムタイプで作るっていうことが何なのか?”っていうのが、ダムタイプで作る場合の一番のテーマになります。僕個人の作品の場合は、こうしよう、ああしようというのは瞬時に決めていけるんですけど、ダムタイプで作るっていうのは“僕はこう思うけど、あなたはどうなのか?”っていう確認作業がほとんど。信頼関係をいかに築くかっていうのが大切。前作の「Voyage」から18年のブランクがあって、お互いの共通言語というか、“こういうものが面白いよね”っていうところからすり合わせをしているから時間はかかります。
──話し合い以外に“システム実験”とおっしゃいましたが、具体的にどんなことをされているのでしょうか?
高谷 最初のころに実験していたのは今回の個展「ダムタイプ|アクション+リフレクション」で展示している「Playback」を並べて、パフォーマーが自分が持っているレコードをかけてみたりとかですね。
──「Playback」は元々パフォーマンス「Pleasure Life」の舞台装置から派生したものですよね?
高谷 はい。「Pleasure Life」はグリッド状の世界の中で人がどうコミュニケーションをするかっていう作品で、パフォーマンスの上演が終わってから、“インスタレーションとして美術館で展示できるものを”と頼まれ、1989年に作ったのが「Playback」です。そのときの「Playback」は上に本当のターンテーブルが載っていたわけではなく、アクリルのディスクを回転させることでそう見せていました。今回の個展で展示したのは、2018年にポンピドゥー・センター・メッスでの個展の際に作ったものがもとになっていて、本当にターンテーブルが載っているんです。それを新作の準備のときに使ってみたんですね。
──「Playback」のプラットフォームを新作で使う可能性があるということですか?
高谷 それはないです。ダムタイプとして何を作るかっていう話になったときに、僕の中では空間的なグリッドのシステム……すごく不自由な空間を作りたくなるんです。グリッドがあると縦か横にしか動けなくてとても不自由ですよね? そういう制約を設けるのがダムタイプらしさの1つかなと。なぜそういう不自由なものにするのかっていうのと、ダムタイプっていうのは芸大(京都市立芸術大学)のアーティストが集まって作ったっていうこともあり、自由に踊れるダンサーが集まっているわけでもないんです。今はダンスをやっているメンバーもいますが、元々ダンサー的な表現はできないパフォーマーが何をしたらいいかって考えたときに、自由に踊れない不自由な空間を作って、その中でうまくやるのを見せたらいいんじゃないかと。新作の準備のときに「Playback」を持ち出したのは、その流れで実験的にやってみただけで、実際の舞台装置にするつもりではないです。
──「Playback」……「Pleasure Life」の舞台セットとはまた違う不自由さを新作では用意する可能性があるのですね。
高谷 何でもかんでもコンピューターでできて、映像も音楽も照明も簡単に同期でき、時間と空間のグリッドを作るのが簡単になった今、新しいメンバーと話をしているのは縦横のグリッドじゃなくて、一筆書きで書いている光の筋のようなものの中に時間的なグリッドが入っていたりとか、ムーブメント的な……例えばこことこのポイントは絶対に何秒おきに通るとか、複雑なグリッドを組めないだろうかと。一見グリッドじゃないように見えてグリッドなのか、グリッドのように見えて全然グリッドではないというのができたら面白いのかな、という話はしています。
──その新作は現段階でどれくらいまでできているのでしょうか?
高谷 えっと……マイナス20くらい(笑)。
──えっ(笑)……3月に上演するんですよね?
高谷 ええ、でも、まあできちゃうんですよね。今回、個展の準備をしていても思ったんですけど、こんなペースでは間に合わないんじゃないかって言っても、絶対間に合うんですよ。それはどういうことかというと、どこかで諦めるんです。その諦めるポイントをできるだけ前に進めたいから焦るわけなんですけどね。パフォーマンスの場合だと、初演したときにどこで諦めているかってこと。例えば「OR」だと初日の舞台は2時間近くもあってすごく長かったんですよ。(古橋)悌二さんが亡くなって、その後に作った最初の作品で、今までみんなで作っていたつもりだったけど、やっぱり推し進める人がいなくなるとむちゃくちゃ時間がかかった。アイディアはいっぱいあるんだけども、どういうふうに構成していくかっていうのがまとまっていなくて、出てきたものを全部やったというのが初日。さっき言ってたテープ編集が全然追いついてなくて、初日の本番が始まったときに僕は最後のシーンのテープをダビングしてました(笑)。“まだ終わりません!”って言ってるのにお客さんが入ってきて、パフォーマンスの途中でもまだダビングしてる(笑)。だから「OR」の初日は僕自身、本番を全然見れてないんです。
──どれくらい上演を重ねるとパフォーマンス作品として完成するのですか?
高谷 いや、だからといって初演が作りかけってことじゃないんです。毎回どんどん新しいアイディアが出てきて、もしそれが整合性を持ってつなげられるなら足していく。「S/N」のころから言っている“ワークインプログレス”っていう考え方ですね。あのころはよくツアーをしていたからっていうのもあるんですけど、共有する時間が長かったので、どんどん足したり引いたりしながらそのときのベストを探っていく。決め決めな感じのインスタレーションとは違って、作品が進化していくのがパフォーマンスの面白みです。
──ワークインプログレスという意味では、今度の新作もそういう道をたどっていくのでしょうか? 現状、京都での2公演しかアナウンスされていません。
高谷 いや、今のところ、本当にその2公演しかやらないんです。だってマイナス20ですから、どっかに持って行ける話じゃない(笑)。別に自信が無いわけではなくて、作れるのは作れますけど、何て言うのかな……パフォーマンスのツアーってかなり前もって計画しないとできないものなんです。「Voyage」までは、出入りはありますけど大体一緒のメンバーでやってきて、ツアーに出ている最後の1年か1年半くらいは、ずっと新作の話をしながらパフォーマンスをやっていた。そこで作っていけたんです。でも、今回は18年ぶりですし、今は各自それぞれ自分のプロジェクトを持っているから、来年とか再来年の予定を今から入れるっていうのが可能かどうか分からないんです。
──今回の上映会に来場してくださった方々は若い人……一度もダムタイプを観たことが無い方が多かったです。なので、新作はなるべく多くの方々に観てもらいたいですね。
高谷 はい、自分もそう思います。本当に観てもらいたいんですよ。
Day 7 -「Voyage」 after talk with 古舘健 (2019年12月1日)

●高谷史郎作品の源流となった「Voyage」
──古舘さんはダムタイプでは新しい世代のメンバーになりますが、「Voyage」の舞台は初演当時ご覧になっていましたか?
古舘 「OR」は高校生の時に京都で、「memorandum」は学生時代に日本初演を生で観ているんですけど、「Voyage」は生で観たことはなくて、実はビデオですら最近まで観ていませんでした。
──本日ご覧になっての感想は?
古舘 やっぱりさすがだなと思う部分と、こういう感じかーっていう部分、両方ですね。
──改めて観ると、古舘さんもかかわっている高谷史郎さん名義の舞台作品に近いというか、その源流を感じますよね?
古舘 そうですね、最後のシーンの航海図とか、同じモチーフがいろいろと使われていますよね。
──今回の東京都現代美術館の個展「ダムタイプ|アクション+リフレクション」でも展示されていましたが、舞台の床材が鏡のようになっていて、スクリーンに映し出される映像と衝突していくように見えるのが、現在の高谷さんの映像手法であるToposcanに通じているようにも感じました。
古舘 ええ、高谷さんの最新作である「ST/LL」での水の床と通じている部分もあるかもしれません。「Voyage」の鏡の床はそもそも漆黒を作り出すためにそうした、と聞いたのでコンセプチャルには違うかもしれませんが、美意識としては共通のものは感じられますよね。最後の地図と重なるように図面が出てますけど、あれも「Chroma」で使われた素材ですし、高谷さんが「Voyage」を1つの起点にいろいろ自分の作品制作を進めてきたんだなとは思います。
──「Voyage」にはそういう高谷色と、暴力的な音の池田亮司色、両方がありますね。
古舘 確かに「Voyage」は高谷さんと池田さんの要素っていうのがすごく強いですね。「OR」や「memorandum」はパフォーマーが激しく動くシーンが多いですけど、「Voyage」はパフォーマーが止まっているシーンが多い……絵として作るっていう傾向がすごく強かったのかなという気がします。
●ダムタイプのメンバーになるということ
──そもそも古舘さんはどうしてダムタイプに関わるようになったのですか?
古舘 ダムタイプを知ったのは高校生のころ……演劇をやっていた兄が教えてくれたのがきっかけです。CSのシアターテレビジョンでダムタイプ特集が放映されてて、それで「Pleasure Life」「pH」「S/N」「OR」と一通り見ました。そのちょっと後くらいにICCで池田さんのライブがあって、プロジェクションされてるオシロスコープを客席で見ながら泣きました。多感な時期でした(笑)。メンバーと直接関わりを持ったのは、僕が2006年に京都に引っ越したときです。知り合いの紹介で大学に勤めていたのですが、そこでダムタイプの泊(博雅)さんや、ダムタイプと関わりの深いデザイナーの南琢也さんが教えられていたんです。そこで“どうやらプログラム使って映像とか音とかできるやつが来たらしいぞ”と聞きつけられ、南さんに制作の手伝いを頼まれたんです。ダムタイプではなく、南さんと上芝(智裕)さんが中心でやっているSoftpadというオーディオ/ビジュアルユニットの作品だったんですが、それが高谷さんとのコラボレーションという形だったので、ダムタイプオフィスに打ち合わせに行くようになったのが始まりです。
──古舘さんはさまざまなアーティストの作品作りにプログラマーとして関わっているのに加え、ご自身もアーティストとして活動されています。“あなたは何者ですか?”と聞かれたらどう答えているのですか?
古舘 よく聞かれるんですけど、難しいんですよね。最近は“アーティスト/ミュージシャン/エンジニアです”と答えるようにしています。
──プログラミングはどこで学んだのですか?
古舘 高校を出てからIAMASっていうメディアアートの専門学校でMax/MSPを勉強しました。2002年にそこを卒業してから東京に行ったんですが、今だと音とか映像をコントロールするプログラムが書けるといろいろ仕事がありますけど、当時は全然なくて、東京で日の目を見ないままちょこちょこライブをやったりVJをやったりしていました。
──そもそも私が古舘さんと初めて会ったのはそのころですよね?
古舘 はい、IAMASを卒業してすぐ……思い出した!5月です。サウンド&レコーディング・マガジンが開催したMax/MSPパッチコンテストのときです。
──コンテストの優秀者を招いてのイベントを西麻布BULLET’Sというクラブで開催したときですよね?
古舘 はい、僕は準優秀賞で、VJをやりに行きました。
──そのときの受賞者がまさか後にダムタイプに入るとは……思いもよりませんでした(笑)。
古舘 ですよね(笑)、その時は本当に関わりがなかったですし。
──上芝さんとお話をしたとき、ダムタイプは古橋さんや山中さん、高谷さんたちオリジナルメンバーの世代がいて、上芝さんや池田さんはダムタイプに憧れて入った世代だと伺いました。古舘さんはもっと下の世代にあたるわけですが、どういう気持で参加するようになったのですか?
古舘 高谷さんと一緒に仕事をするようになったのは2008年くらいで、別に僕からダムタイプに入りたいって言ったわけではなくて、たまたま一緒にやるようになった感じです。高谷さんのプロダクションとしては、入りたいって言ってきた人を入れるというより、高谷さんが必要に応じて探して、気の合った人を集めている傾向が強いと思います。
──では、ダムタイプのメンバーになる……“今日からお前はメンバーだ!”という何か明確な区切りはあるのですか?
古舘 僕に関して言うとダムタイプのメンバーになったのは2014年。今回の個展でも展示されている「MEMORANDUM OR VOYAGE」という作品を作ったときにメールアドレスを貰ったんです……“これでキミは今日からダムタイプだ”と(笑)。
──メアドを貰うとダムタイプ?
古舘 そうなんです(笑)。
──では、新世代の一人である原摩利彦さんもメアドを持っている?
古舘 はい、彼もメアド持ってます。今回の個展の準備で濱哲史と白木良っていう若手の2人……彼らはポンピドゥー・センター・メッスのときはメアドを持ってなかったんですが、与えられました(笑)。
──昇格基準って何なんでしょう?
古舘 タイミングだと思いますよ。
──その判断はどなたが?
古舘 高谷さんがサーバーの管理もしているので、直接的には高谷さんです。メアドをもらったらダムタイプってちょっと冗談めかして言ってますけど、多分その辺は曖昧だと思うんですよね。僕自身としても別にダムタイプであろうがなかろうがどっちでもいい。作品を作る段階で一応メンバーってしておいた方がいいだろうみたいな判断ですかね。ポンピドゥー・センター・メッスでの展示のときに、入口のすぐ横に関わったメンバーの名前が掲示されているんですが、僕より上の世代のダムタイプのメンバーの人たちがそれを見て“ああ、新しいメンバーが入ったんだ”と知ったという話を聞きました。メンバー全員に承認を取って“今日からこいつもダムタイプだ”みたいな儀式があるわけではないです(笑)。
──そういう意味で緩やかな集団なんですね。
古舘 そうですね。実際は気が合う、合わないっていうのが大きい気はするんです。
──別にそれはダムタイプの方々が気難しいということではなく?
古舘 気難しい部分が無いことも無いですけど、それよりも、言葉にしなくても理解できるみたいな、ある種の似通ったセンスを求めてるんです。だから一緒に仕事をしていても皆まで言わない部分がある……これってかっこいいよねって言った時に、“ああ、そうですよね”って言える人なのか、説明しなきゃいけない人なのかによって仕事の仕方って変わってきますから。
──それは感覚的な部分ですか、それとも知識?
古舘 どっちもですね。
──古舘さんはそこを乗り越えた?
古舘 まあ気が合ったってことなんですかね(笑)。
●「MEMORANDUM OR VOYAGE」のクリエイション
──先ほどお話に出た「MEMORANDUM OR VOYAGE」ですが、「OR」「memorandum」そして「Voyage」という3つのパフォーマンスで使われた映像がもとになっているインスタレーションですが、何か新たな素材は足していますか?
古舘 「memorandum」でパフォーマーが踊っているシーンについては撮影し直しています。「memorandum」の上演時、パフォーマーは実際にその場で踊っていたので素材としての映像は無いんですね。なので京都で小さな劇場を借りて、舞台で使ったのと同じ半透明のスクリーンを張り、照明を入れて撮影しました。それ以外は、CGで描いているラインは新しく作っていますけど、音や映像の素材はオリジナルのものを使ってます。
──オリジナルの素材をもとに、具体的にはどのように制作されたのですか? 全部コンピューターで作業されているのでしょうか?
古舘 はい。openFrameworksという、ちょっとクリエイターに対して使いやすくなってるC++のライブラリーを使って制作しています。それで映像のひとつひとつの素材をシーンとして作っていって、それをタイムラインに合わせてトリガーしています。タイムラインの管理はAbleton Liveに自作のMax for Liveのモジュールを入れて音に合わせて展開していくようにして、最終的に決まったらタイムラインはテキストファイルに書き出してopenFrameworksだけで動きます。
──openFrameworksはメディアアートの現場でよく使われてますが、どんな点が優れているのでしょう?
古舘 C++だけで何かを作ろうと思うとすごく大変なんですよね。おまじない……それこそおまじないって言うんですけど、それを書いて、ようやくウィンドウがぽんと1つ開くみたいな。そこに描画しようと思うとまたいろんなおまじないを書かなきゃいけない。でも、openFrameworksのライブラリーを使うと、1つコマンドを書くだけでぽんとウィンドウが開く。線を1本引いたりとかムービーを再生したりとか、クリエイターにとって役に立つ処理がすぐできるので使いやすいんです。あと、コミュニティベースで作られているので、標準で機能が付いてなかったとしても、アドオンっていう形で世界の誰かしらがモジュール化して足せるようになっているのも大きいですね。
──以前、高谷さんの「Chroma」の取材でびわ湖ホールに伺ったとき、2日目の上演の直前、高谷さんが古舘さんに“健ちゃん、舞台床に投影している映像をもっとホリゾントの方に延ばして”とおっしゃっていて、すごい注文だなぁと思ったんですが、古舘さんは“分かりましたー!”って言って、すぐに映像をびゅっと延ばしたのでビックリしました。C++だったら“分かりましたー!”って言った後にカタカタ打つしかなかった?
古舘 ですね、“3時間ください!”とか言って……それこそ以前のビデオ編集だったら一晩くださいって(笑)。
──昨日のトークで高谷さんから「OR」のときは本番が始まっているのに上映用のビデオテープをダビングしていたという話を伺いました。
古舘 伝説のやつですね(笑)。「MEMORANDUM OR VOYAGE」に関して言うならば、最終的にタイムラインは決まっているので、展示する際は実はビデオでいいんです。実際、ポンピドゥー・センター・メッスで「MEMORANDUM OR VOYAGE」を展示したときはムービーファイルを再生していました。でも、作って行く最中では変更が頻繁に起こるし、それにすぐに対応しなきゃいけないので、openFrameworksのようなソフトウェアでその場で作っていくのはアドバンテージがあると思います。
●ダムタイプ作品にとって重要な“ネジ”
──今回の個展でのインスタレーション「pH」はポンピドゥー・センター・メッスのために作ったものを持ってきたのですか?
古舘 そうですね。ただ、メッスで展示した時に起こった不具合を直したりはしてます。
──パフォーマンス「pH」に参加されていた上芝さんが、今回のインスタレーション版をとてもきれいだと激賞されていました。以前の工作精度とは比べものにならないと。なぜそこまできれいにできるようになったのですか?
古舘 今はああいうものを作ろうとしたとき、奇麗なパーツが買えるんですよ。サイズを決めて発注したらその通りに切って送ってくれるようなサービスもあるので。
──このインスタレーション「pH」について古舘さんはどういう関わり方をされているのですか?
古舘 「pH」に限らずですが、ダムタイプの場合、まずはどんな作品を作ろうかというミーティングから始まります。過去の作品をモチーフにしようっていうのはもう決まっていて、「MEMORANDUM OR VOYAGE」で「OR」「memorandum」「Voyage」をモチーフにしたので、次にやるとしたらと「pH」か「Pleasure Life」かなと。元々「Pleasure Life」「pH」「S/N」はそれぞれのインスタレーション版もあるんですけど、それらとはまた違う、今らしい解釈で作れないかというところがありました。今回の「pH」に関しては、あの形になるまでにアイディア出しからみんなでワイワイやっていますね。あの形に決まってからは、他の作品全部にも言えるんですけど基本的なハードウェア……大きな構造物とかに関しては高谷さんがデザインする。それに対してモーターを回すとか、LEDを付けるとか、基板を作るとかのエレクトロニクスの部分に関しては僕が担当しています。
──古舘さんはコンピュータープログラミングだけでなく、メカトロニクス的なことまでやるのですね?
古舘 やりますね。Arduinoのようなフィジカル・コンピューティングデバイスを知ったのをきっかけに、ハードウェアをプログラムで制御できるのが分かったので、プログラミングを軸にしてできることは何でもやっています。電子回路についても、部品1つ1つのシンプルな機能があって、それを組み合わせて何かシステムを作るっていう意味ではプログラミングと変わらない。今回の「pH」では裏に1つボックスがあって、その中にmbedっていうマイクロコントローラーが入っていて、C++とそれ専用の言語でプログラムが書き込めるので、コンピューターを使わずにスタンドアローンでトラスが動かせるんです。
──プログラミングを使ったアートというと、一昔前はコンピューターから出る音や映像だけというイメージが強かったですが、実際の物を動かすケースが増えているのですね。そう言えば、今回の個展の設営を見学させていただいたとき、古舘さんと原摩利彦さん、濱哲史さんが「pH」の組み立てを……黙々とネジを締めていて、現場はガテン系なんだなと思いました。
古舘 そうですね、重いものも運ぶし(笑)。
──何かいい光景というか、ああ、この人たちは本当にダムタイプに入ったんだなと思いました(笑)。
古舘 そうですね、ダムタイプに入ったら、まずアーレンキーていう六角ナットを回す工具を買わなきゃいけないんですよ。
──メアドもらったらすぐに?(笑)
古舘 そうそう(笑)。それも日本製の精度がちゃんと出てるやつ買わないといけないんです。
──今回、藤本さんもトークでお話してくださいましたけど、昔からとにかくダムタイプはたくさんのネジを締める集団だったと。
古舘 ひたすら締めますね。ダムタイプがそうだっていうのもありますし、高谷さんが言うなれば“ネジの作家”だと僕は思ってるんですよ。何か物を作る時にネジにこだわるんです。高いネジを買ってきて……メッスのときは恐ろしいことにネジの予備がない。ギリギリしか買ってないんです(笑)。いろいろこだわりのポイントもあって、プラスのネジは機械で締めてマイナスのネジは手で締めるとか、そういうところから始まって、ネジの頭の高さとか、それに合わせたワッシャーとか、ホントにすごいです。
──今回の個展の「Playback」もとても奇麗なフレームで出来上がっていました。あれも高谷さんが設計して、みんなでネジを締めているのですね?
古舘 そうです。高谷さんが選んできたこだわりのネジを……“無くすなよ、落とすなよ”と(笑)。最近はミスミという会社のを使っているので規格品が多いですけどね。
──「Playback」では各プラットフォームがターンテーブルでレコードを再生していますが、それぞれがレコードのどの箇所を再生するかはコントロールされているのですか?
古舘 実際のところは1台のコンピューターがそれぞれのプラットフォームにコマンドを送って制御していますが、それぞれが自立したというか、他のプラットフォームのことを意識しながら次にレコードのどの箇所をかけるかを判断していると見えるようにプログラムされています。
──単にランダムにレコードが再生されているわけではなく、1つのプラットフォームがある箇所を再生していたら、隣接するプラットフォームはそれを把握して同じ箇所がかからないようにしている?
古舘 そうですね、ちゃんとコンポジションされている……アルゴリズミックにコンポジションされています。
──コンポジションというキーワードはダムタイプの方々がよく使いますよね。古舘さんにとってコンポジションはどんな意味を持っていますか?
古舘 「Playback」に関してならば“作曲されている”っていうことですよね。コンポジションってまさに言葉の意味としては作曲ですけど、「Playback」の場合、一般的に言われる作曲はしてないですがルール付けはしています。例えば、ある時間では最小で2台、最大で6台が確率で選ばれてある特定の音を鳴らす、とか。その選ばれ方も、鳴っているプラットフォームに隣接するプラットフォームが選ばれるようになっている。1つのプラットフォームから鳴り始めた音が、だんだんと空間的に広がっていくようなイメージですね。そんなことをプログラムで作っておいて、それがいい感じになるようにルールを調整していくというのを僕はコンポジションととらえています。
●集団創作の理想を再び追い求めている新作
──ダムタイプとしての新作が3月に予定されています。古舘さんをはじめたくさんの方が参加すると伺っています。
古舘 そんなに多くもないかなと思います……パフォーマーの数で言ったら「Voyage」の方が多いですし。ただプログラマーとかテクニカルの人数は多いですね。
──音楽家が多いという話が……古舘さんのほかに原摩利彦さん濱哲史さん、そして山中透さんも参加。池田亮司さんも参加されるというのは本当ですか?
古舘 遠くからサウンドファイルが送られてくるらしいって話を聞いたことはありますね(笑)。全員が1曲ずつ作ればそれだけで舞台が終わってしまいそうですね(笑)。
──古舘さんは新作に音楽だけでなくかなり深く関わっているのでしょうか?
古舘 そうですね。準備が始まってからあまりにも話が進まないので、“じゃあ今回僕がリードします”みたいなことを言って1回リードしてみたんですが、やっぱりなかなか進まない(笑)。
──やはり18年ぶりにパフォーマンスの新作を作るとなると簡単には進まない?
古舘 ダムタイプは集団創作……誰もディレクションを取らずにみんなで作っていくとよく言われますが、「OR」以降は半分幻想だと思うんです。池田さんが音を作り、高谷さんが映像を作ることでタイムラインはガチガチに決まりますからね。でも、今作っている新作はその幻想というか、理想的な状態っていうものをどう本当に実現できるかっていうトライをしているようなことなのかな、と思っています。なので結構ミーティングは重ねていて、その中で技術としては最近こういうものがあるよねっていう話をしたり、それに対してパフォーマンスの人がリアクションしてくる時もあるし、してくれない時もある。そういうアイディアの投げかけ合いをして、パフォーマーからのアイデアをテクニカルに延長してシーンができることもあるし、テクニカルな要素をパフォーマーが解釈して何かシーンに仕立て上げることもありますね。
──大変な作業だと思いますが、今から新作を拝見するのをとても楽しみにしています。本日はどうもありがとうございました。
イベント情報

京都を拠点に世界的な活動を展開するメディアアーティストグループ=ダムタイプ。結成35周年にあたる本年、東京都現代美術館にて大規模な個展「ダムタイプ|アクション+リフレクション」が開催されていますが、それに連動する形で、彼らが過去に上演したパフォーマンス作品──「036-Pleasure Life」「Pleasure Life」「pH」「S/N」「OR」「memorandum」「Voyage」の記録映像を、御茶ノ水Rittor Baseにて7日間にわたって上映します。ダムタイプのパフォーマンスを観たことがない方にとってまたとない機会となるでしょう。また、毎日19時からの回では、上映後に制作にかかわったメンバーを招いてのトークイベントも開催。比類無きレベルのクリエイションがどのように行われてきたのか、あらためて振り返っていただくことにします。映画館やクラブに負けない音響システムを備えた御茶ノ水Rittor Baseで、故・古橋悌二、そして山中透、池田亮司らが作り上げたサウンドを、ぜひ爆音でご体験ください!
<DUMB TYPEパフォーマンス作品連続上映会>
日時:2019年11月25日(月)〜12月1日(日)
会場:御茶ノ水Rittor Base
入場料:1,500円、2,200円(トークイベント付き上映回)
上映作品:「036-Pleasure Life」「Pleasure Life」「pH」「S/N」「OR」「memorandum」「Voyage」
上映時間: ①11:00〜 ②13:00〜 ③15:00〜 ④17:00〜 ⑤19:00〜(トーク付き上映)
*開場は各回上映開始の10分前になります。
トークイベント出演:山中透、藤本隆行、上芝智裕、高谷史郎、古舘健
トークイベント司会:國崎晋(御茶ノ水Rittor Baseディレクター)
主催:リットーミュージック
協力:ダムタイプオフィス
*映像の解像度が粗いもの、映像と音声にノイズが乗っているものがあります。あらかじめご了承ください。
-上映作品-

(photo: Kazuo Fukunaga)
《036-Pleasure Life》
フリースペースの空間はアルミニウムの壁面で覆われ、観客は2メートルの高さから階段状に仮設された観客席から舞台を見おろす。舞台正面の壁には4台のビデオモニターが埋め込まれ、オシログラフなどの信号や様々なイメージの映像、ビデオカメラから挿入されるライブ映像がミックスされ映し出される。フロアは人工芝で区画された36枚のパネルに、天井に設置されたスライド・プロジェクターから写真・文字や記号・抽象的なパターンが映し出される。これらの情報や刺激に4人の人間が反応・行動し、あるいはこれらのメディアに働きかけることによって進行するライフフォーメーションゲーム。
■パフォーマンス上演:1987年 アートスペース無門館(京都)
■出演:古橋悌二、薮内美佐子、カティア・サゼヴィッチ、ジェイムス・シンクレア
■撮影:1987年 アートスペース無門館(京都)
■編集:古橋悌二
■81分 カラー 1987年 © dumb type
《Pleasure Life》
 (photo: Kazuo Fukunaga)
(photo: Kazuo Fukunaga)
「プレジャー・ライフ」、それは人間とテクノロジーを巡る環境の物語である。コロニー、仮想の未来都市。高度にシステム化され自動化された快適な生活。舞台は格子状に分割され、コンピュータ制御のさまざまな装置がメッセージやノイズを発し、一見調和的だが時としてシステムが反乱を起こし極度な不調和を引き起こす空間の中で、4人の登場人物が現代のわれわれの生活を模倣する……。京都で活動を開始したダムタイプの東京初公演、また初のワールド・ツアーの幕を開ける作品である。
■パフォーマンス初演:1988年 原宿クエストホール(東京)
■出演:古橋悌二、薮内美佐子、カティア・サゼヴィッチ、ジェイムス・シンクレア、大内聖子
■撮影:1988年 京都府民ホール・アルティ(京都)
■59分 カラー 1988年 © dumb type
《pH》
 (photo: Shiro Takatani)
(photo: Shiro Takatani)
《pH》というタイトルは化学用語の水素イオン濃度指数に由来しており、パフォーマンスは二項対立の図式にそって(問い/答え、イメージ/言葉、事実/虚構、公/私、現実/非現実など)13のシーンから構成されている。このパフォーマンスのヴィデオ化にあたり、日本衛星放送WOWOWとのコラボレーションが実現した。さまざまな公演会場で、さまざまな視点・角度から撮影された膨大な映像が、ダムタイプの古橋悌二によって編集され、単なる記録映像を超えたひとつの映像作品に仕上がった。TTVV-Riccione(イタリア)のSole d’Oro(黄金の太陽)賞、IMZダンス・スクリーン92(ドイツ)のベスト・ステージ・レコーディング賞を受賞。
■パフォーマンス初演:1990年 スパイラルホール(東京)
■出演:ピーター・ゴライトリー、砂山典子、田中真由美、薮内美佐子、古橋悌二
■製作:日本衛星放送WOWOW+ダムタイプ
■協力:株式会社EGG
■映像演出:古橋悌二
■68分 カラー 1992年 © WOWOW + dumb type
《S/N》
 (photo: Yoko Takatani)
(photo: Yoko Takatani)
タイトルは「シグナル/ノイズ」を意味し、音響機器等で信号に対するノイズの比率を表す「S/N比」に由来する。今日の社会が直面する切実な問題であるジェンダー、エイズ、セクシュアリティなどを軸とし、人種、国籍、あらゆるマイノリティや性差別など、現代社会が抱える諸問題を正面から捉え、パフォーマンスのみならず、周囲のさまざまなコミュニティとの交流・連携といった具体的なアクティヴィズムまでも巻き込み展開された。この作品で、構想・演出、そしてパフォーマーとしても出演し、舞台上で自らゲイでありHIV感染者であることを公表していた古橋悌二は、1995年10月29日エイズによる敗血症のため逝去。古橋の死後も、古橋不在の《S/N》は5カ国・6都市で上演され多くの人々に影響を与え続けた。
■パフォーマンス初演:1994年 アデレード・フェスティバル(オーストラリア)
■出演:石橋健次郎、鍵田いずみ、小山田徹、ピーター・ゴライトリー、砂山典子、高嶺格、田中真由美、古橋悌二、薮内美佐子
■撮影:日本衛星放送WOWOW(1995年 スパイラルホール/東京)
■編集:高谷史郎
■ 90分 カラー 1995-2005年 © dumb type
《OR》
 (photo: Arno Declair)
(photo: Arno Declair)
1995年に急逝した古橋悌二が死の直前に書き残した次回作のコンセプトノートを出発点に制作された。それは古橋が家族や恋人を亡くした体験から「生と死の境界について、どれほど科学はその境界を制御できるか、どれほど我々の精神はその境界を制御できるのか」というアイディアが書かれていた。舞台は何も無い真白な空間で、半円筒形に張られた白いスクリーンだけで構成される。強力なストロボ照明によるホワイトアウトの創出と強烈な音響・映像。「自己と非自己のボーダー」「生と死の間に横たわるグレイゾーン」などに関する様々な考察が試みられた。《OR》というタイトルには、二者択一(A or B)、二進法(binary system)、0 (zero) Radius=見えない円、オペレーション・ルーム等の意味が含まれている。
■パフォーマンス初演:1997年 「VIA フェスティバル」ル・マネージュ国立舞台、フランス
■出演:石橋健次郎、大内聖子、川口隆夫、砂山典子、田中真由美、前田英一、薮内美佐子
■撮影:シアター・テレビジョン(1997年 パークタワーホール/東京)
■協力:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
■映像編集:高谷史郎
■音楽編集:池田亮司
■71分 カラー 1998年 © dumb type + Theater Television
《memorandum》
 (photo: Kazuo Fukunaga)
(photo: Kazuo Fukunaga)
プロジェクトに関わるメンバーが「記憶」について一人一人の考えや意見を交わすことから出発し、そこで発生してくる共鳴や差異を様々なかたちで発展させて出来上がったオムニバスのようなこの作品は、圧縮された多くの記憶の断面を時間軸上に組み上げて出来る、一本の直線で出来た迷宮を舞台上に創り出す。舞台全面を覆う半透明のスクリーンは、まるで記憶のように、向こう側にいるパフォーマーの姿を、スクリーンに近づくとはっきりと、遠ざかるとぼんやりと曖昧なものにする。情報が極限的に集積され舞台上を覆う映像と音響の流れの速度と密度が人間の知覚の限界に迫るとき、それは過剰露出されたフィルムのように真っ白な状態に近づいてゆく。あたかも落下しながらほとんど静止して見える凍った瀑布のように。
■パフォーマンス初演:1999年 「Festival de danse」ル・マネージュ国立舞台(フランス)
■出演:大内聖子、川口隆夫、砂山典子、田中真由美、藤原マンナ、前田英一、薮内美佐子、尾﨑聡
■撮影: 虹映社(2000年 シアター・ドラマシティ/大阪)
■映像編集:高谷史郎
■音楽編集:池田亮司
■71分 カラー 2000年 © dumb type
《Voyage》
 (photo: Kazuo Fukunaga)
(photo: Kazuo Fukunaga)
80年代から90年代にかけて日本経済がバブル絶頂期へと突き進み、バーチャルな消費ゲームと情報過剰の社会に対しシニカルな視点で作品を制作し発表してきた私たちは、21世紀の現在、情報というものがいかに限定され操作され偏ったものであるかを改めて知ることとなる。現代のテクノロジーにおいて私たちはもう道に迷うことはない。GPSやナビゲーション・システム、携帯電話でも現在位置がわかる。しかし、これらのテクノロジーのどれが、私たちの心の居場所を教えてくれるだろうか。舞台上では二人の人物が互いに身体をすり合わせるほど近くにいるのに相手が見えていないかのように互いを探し続けている。舞台全面に鏡の床が設置され、漆黒の暗闇と無重力を生み出し、時間と空間の様々な概念の「旅」が描かれた。
■パフォーマンス初演:2002年 トゥールーズ国立劇場(フランス)
■出演:大内聖子、川口隆夫、砂山典子、田中真由美、平井優子、藤原マンナ、前田英一、薮内美佐子
■撮影:2004年 山口情報芸術センター [YCAM]
■編集:高谷史郎
■70分 カラー 2004年 © dumb type
-time table-
●11/25(月)
11:00- 「S/N」
13:00- 「OR」
15:00- 「memorandum」
17:00- 「Voyage」
19:00- 「036-Pleasure Life」+ トークゲスト:山中透
●11/26(火)
11:00- 「OR」
13:00- 「memorandum」
15:00- 「Voyage」
17:00- 「036-Pleasure Life」
19:00- 「Pleasure Life」+ トークゲスト:山中透
●11/27(水)
11:00- 「memorandum」
13:00- 「Voyage」
15:00- 「036-Pleasure Life」
17:00- 「Pleasure Life」
19:00- 「pH」+ トークゲスト:藤本隆行
●11/28(木)
11:00- 「Voyage」
13:00- 「036-Pleasure Life」
15:00- 「Pleasure Life」
17:00- 「pH」
19:00- 「S/N」+ トークゲスト:藤本隆行
●11/29(金)
11:00- 「036-Pleasure Life」
13:00- 「Pleasure Life」
15:00- 「pH」
17:00- 「S/N」
19:00- 「OR」+ トークゲスト:上芝智裕
●11/30(土)
11:00- 「Pleasure LifeE」
13:00- 「pH」
15:00- 「S/N」
17:00- 「OR」
19:00- 「memorandum」+ トークゲスト:高谷史郎
●12/1(日)
11:00- 「pH」
13:00- 「S/N」
15:00- 「OR」
17:00- 「memorandum」
19:00- 「Voyage」+ トークゲスト:古舘健
